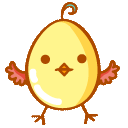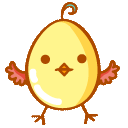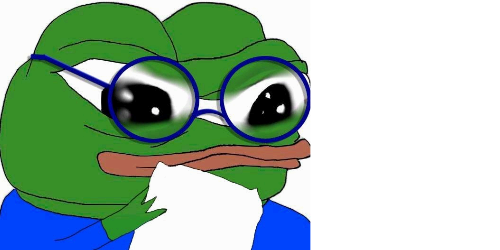50年前まで『山窩(サンカ)』とかいう独自の言語を使って山を渡り歩く謎の民族が日本に居たらしい これ半分ケンモジだろ [959542443]
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
妖怪サトリとかヤマワロとか山に出てくる
人型妖怪の元ネタって都市文明の連中が山の中で
こういう連中に遭遇して生まれたのかな?
サンカ伝説の半分以上が三角寛が考えたフィクションなんだけど
そう言うとQアノンみたいな奴がキレ散らかしてくるんだよな
ジジモメンだけど、そいつらは知らんけどガキの頃に渡り鳥みたいに特定の時期だけ地元の河川に船を留めてそこで船上生活してる家族が居たわ
その河原は俺等の遊び場だったから、その家族のガキも混じって遊んでたけどアイツラって何者だったんだろ
兄と妹がいて、兄は俺と同年代だと思うが学校にも行ってなかったし
山奥民はいただろうけど山小屋作って住んでたろ?
渡り歩くってなに?
サンカ研究の第一人者が捏造しまくってたやつやろ
ほぼ嘘という
日本の山なんてろくに食うもんないだろ
冬は
熱帯地方の密林じゃあるまいし
暮らしていけるわけねえわ
そういう暮らししてた人たちはいただろうけど、
山窩文字とかあの辺は全部三角寛の創作だべ
>>18
そして一般人が持ってる山窩のイメージはその捏造がほぼ全てという惨状 山深い県とか、修験道の行者とかならいただろうけど
創作のサンカなんておらんだろ
1000年後にはシンゾーも神格化されて実際にはいなかった扱いになるのかな
半世紀ぐらい昔にもポツンと一軒家みたいな生活を送っていた人たちが少なからずいた
というだけの話なんだよな
>>15
どこの話よ
昭和中期まで四国にそういうスタイルの漁師がいたって話は聞いたことあるが まあ、ある程度の移動性生活を送る戸籍に乗らない人たちは近代まではいたのは確か
水上にしろ山奥にしろ
山で独自の文化、社会を築けるほどスペースの余裕が無いだろ
昔は木を燃料に使うから相当な所まで禿山で畑だったりする
>>15
河童伝説の元になった人たちだろ
いやマジで >>25
三角寛のは創作だろうけど山で不定住生活してる集団が存在して明治政府が取り締まったってのは事実だろ? >>13
違うだろ 単に山奥で生活してる小ぶり集落
辞書によると狩猟・竹細工等を業として生活してたらしい >>3
「もーちがおるんよ…」
「ユピーッ!」
「メイベルちゃん」
「ゴミクヅ死ねにゃ!」
「をれは~」
「グッポ梶田消えろ!」 山奥で炭焼きでもしてた人たちなんじゃないの?
日本社会が輸入燃料に切り替わって山を下りていなくなっただけでは?
>>15
横浜の中村川には結構な水上生活者がいてそういう人のための小学校まであったからその類じゃねえかな >>42
で結局グッポ梶田って何なの?
芸人? 今は廃村になってるけど
昔は日本は山の奥の奥まで集落があったんだから
集団でうろつけるほどの自由な大地は日本には残ってなかっただろう
静岡県と長野県の県境とか
天空の村か?と思うような斜面にまで集落作って畑にして
住んでるんだから
現サントリー社長の新浪さんは
水上生活者の末裔やな
>>15
それは普通につい最近までいた
昔の港湾は浅くて大型船舶が近寄れないから
小舟で荷降ろしする人たちがいたのよ
氷河期世代ならガキの頃にその名残をみたことあるんでは 死ぬほど奥深い南アルプスの山々も全部、林業のための私有地だし
サンカという放浪者の存在が許されるほど
日本は広くない
>>46
元町の近くのだるま船が撤去されたのってほんの半年くらい前だよな >>55
江戸時代で3000万人
明治時代で5000万人
都市化してないから農村、山村人口は
昔の方が今よりはるかに多い >>15
はしけとかそういうのでしょ
俺は横浜だからそういう人たちがいた記憶がうっすらある >>4
ホームレスというか日本版ジプシーって言い方があっているんだが
これ嘘だったんだ、本当かと思ってた >>50
ドライブしててそういうの見かけると平家の落人かなとか思うねw >>15
水上生活者は全国的に見られたけど1960-70年に陸上生活に移ってる >>54
ただ、国土面積や緯度でいくと
日本列島とイギリスってだいたい同じ面積の
島国で地理的に似てると思うんだけど
ああいうとこには渡り歩いて暮らしてる
へんちくりんなのが居る。
ジプシーがそう。まあ連中は謎でも
なんでもないけど。
英文学、イギリスやアメリカの小説を読むと
欧州にはジプシーという住民票やその国の国籍を
もってるのかどうかも怪しい浮浪者まがいの
連中が伝説の存在どころかまるで日常のできごと
のように登場してくるのにビビる。
しかも「○○公爵の山林の一角にそのジプシー小屋
はある」みたいな描写で
貴族の私有地の一部分を勝手に占拠して池で釣りを
して魚食ったりしてる感じなんだが
「どうしてイギリスの領主サマは浮浪者どもを
追い出さないんだ?」と不思議に思いながら
読むんだが。
ジプシーとかいうのが山林や貴族の私有地の
一部に勝手に居座るってのは欧州人的にはOK
なのだろうか。
こっちは伝説の存在でもなんでもなく、小説の
舞台にまるで「居て当たり前」みたいなツラして
登場してくる浮浪民ではあるが。 そんなもん居たら江戸時代に全員捕まってるわ
江戸時代舐めんなよ
>>20
はい。独自文化持つ必要も無いし、狭い日本で持ち続ける事も出来ないからね。 >>54
なんの意図があってこんな嘘つくんだろう?
そんなとこほとんど国立、国定公園の国有地でしょ 文明の灯りが隅々を照らす前に
山奥に住む放浪民はいたのだろう
被差別性の物語や反権力の物語を付与するから
話に嘘が混じる
>>70
実際迫害されまくってたけどしぶといから諦めたんじゃね 明治期に主に官憲によってサンカと総称された戸籍外集団がいたのは事実
主に木工細工によって定住民と取引して糧を得ていたのも事実
彼らが単に食いつめた貧困層+逃亡犯だったのか、中世?近世?から山間部に移った集団だったのかは不明点が多い。地域ごとに起源が異なる可能性も高い
彼らが独自の文字を持っていた・日本人とは全く異なる生活習慣を持っていたというのは誤り(定住民とは異なる、なら正しい)
地域ごとに一定の方言があったのも確からしい
>>35
うむ中国の路上生活者がどーたら言う奴らがいるが、近代化中は居て当然 でもいまこそやったら快適な暮らし送れそう
良い温泉というのは普通山奥にあるしいまの日本は高温多湿なので冬以外は北から南まで高地だけが避暑地だし
猪いるからたんぱく質源はある
冬だけ南の平野部で住んであとは山の中移動生活するのが最善じゃないか?
>>70
イギリスと日本は可住地面積が全然違う
日本は山だらけで、かつ人口密度が高いから
山の奥の奥の奥まで集落がある
本当に信じられないところまで集落が作られてる
ポツンと一軒家になってるところが
昔は全部集落だった >>1
この画像でひと目で嘘だと分かるな
日本は裸で生きていけるような気候じゃない 一般的なイメージのサンカは嘘だけど、サンカはいたでしょ、しかもつい最近まで
>>73
南アルプスの赤石山脈は東海フォレストの持ち物だぞ >>82
ああ、アガリビトだったわ
基本マッパで人から神になりかけのやつ >>70
捕まえてきて労働力にするのに都合が良かったんじゃね? どこかに居を構えただけだと思うけどね
マタギになってそれも途絶えたようだが
>>77
後北条家滅亡後の風磨一党は
既に徳川家に従っていた甲賀伊賀の忍者集団からハブられたせいで
山間部に隠れ住んで
峠の追い剥ぎや盗人稼業で暮らしていたりしたんだよな 大昔、ど田舎の山に住む豪農育ちの曾祖父さんは普通の末っ子として丁稚奉公に出されてたから俺の身元は大丈夫
>>81
地域によって平家の落ち武者の末裔の集落と
あとは近代でも戦後満州から引き上げて来た人達に山の中自分で開拓してコメ作るなら土地をあげるとかいうなんでんかんでん私財法みたいなのがずっと続いてたから
流れ者が勝手に住み着いて最終的に自分の土地にするというのは別に不思議な事ではないような 嘘ってまじなん
一時期面白くてサンカの本めっちゃ読み漁ってたのに本当ならショック
>>88
南アルプス国立公園35,752haのうち私有地は3811haだけなんだが >>75
>実際迫害されまくってたけどしぶといから諦めたんじゃね
ヒトラーはこのヨーロッパのそこら中にいる
よくわからん浮浪民をユダヤ人のついでに
殺そうとしたんだよな、確か 実際に車で日本全国特に山の中回ると余所者を監視しやすい道であったり実際に監視されたり詮索されたりよく感じるわ
>>71
関所を通らずに山を自由に動き回っていたというイメージでもう無理があるんだよな
そんな集団が各地にいたら大きな問題になるはずだが江戸時代当時の資料にそれらしいものが無い
そいつらに関所破りのサポートを頼む文化も成立するはずだが全く見ないし
あと山の中で定住せずに狩猟採集のみで生活していくというノウハウや文化もちっとも残ってない
そいつらが里に降りて吸収されたとしても何かしら様々な痕跡を留めるはず 俺も調べたのが7,8年前だからうろ覚えだが、三角寛の創作・捏造が広まってしまっただけで、漂泊民としてのサンカは存在してるよ
21世紀以降のサンカ研究の本を読んでみると良いと思う
沖浦和光がオススメ
>>101
平家の落人村みたいのは結構あるけど、あれも後付けの適当なのも多いんだろうな 似たような山伏はどうなんだ?
比較的最近まで実際にいたんやろ
遠野物語に出てくる山男と山女みたいなのとは違うのか
>>103
東海フォレストの林有地は24430ha
間ノ岳、悪沢岳、赤石岳、農鳥岳、塩見岳、荒川岳など全部含まれる >>109
山窩と被差別部落を関係付けて語る論には興味無いわ
イデオロギーがデカすぎて事実がちっとも見えん >>70
中世では実際、捕まえて処刑したりしている
近世になると「人道的に」
結婚を禁止したり教育を施したりして
同化政策がもちいられた 天保異聞妖奇士とかいう当時誰も理解できなかった土6アニメ
>>112
山伏は今でもいる
千日回峰行達成のニュースが数年前あったでしょ 第一人者が捏造して意味分からなくなってる王道こゴッドジャップパターン
国民は自助とか言って山で住んでる方がマシなレベルの末路
くまじゃなくておっさんのうめき声が山から聞こえる未来も近い
>>112
修験者はまだいるよ
山岳系仏教の実践者という意味で この手の研究してるけど出自バラバラすぎて一概に何がルーツか説明できないし本人特定できるようになっちゃうから本にも纏められないんだよね
例を挙げると山賊ルーツもあるし言葉喋れないから溶け込めなかった奴もいるし家がないし税払いたくないから転々としてる人もいたし
>>112
山伏も今もいるよ笑
多分知りたいのはかつてのように山師や薬売りとして生活している人の事なんだろうけど、今はいないと思う
定住して霊山の麓で薬宿やってたり、宿坊経営なんかやってる >>111
まあ平家の落ち武者というか下らない争いやめて鑑賞されずにノンビリ暮らしたい人というのはいまと同じように昔もいたと思う
西日本でも東日本でも山の中で蕎麦をメインで食してる地域訪れるとそんなイメージがある
猪や鹿や熊の方が栄養源として良さそうだが >>70
ジプシーなんてわざわざ小説読まんでも普通にいるだろ
若い人にとって家がないってのはそんなに珍しいことなのか? >>124
ロールスロイスに乗って京都の祇園に繰り出す人たちですね
わかります 昔はちょくちょくいたよな
山で炭焼きして待ちに売りにきてた人たちのことだろ
とはいえ見かけたのも昭和40年位までか
>>124
彼らは南北朝時代の前から居たの?
なんとなく勝手に後醍醐天皇が南朝つくった頃の護衛達がつくったイメージ持ってたが >>124
修験者といえば剣岳の山頂にあったグッズは修験者が置いてったらしいけど登れたのが凄いといつも思う サンカは初めて聞いたけど、年貢逃れに山間部でひっそりと集落を作ったのが町の起源とか言われてる地域もあるらしいじゃん
その定住しなかったバージョンとかなんかな?
>>132
単なる田舎者とはなんか違うんだよな
一ヶ所に定住せずに山を移動しながら炭焼いてる人たちが居たんだよ >>116
竹細工売ってる人らの祖先がそうじゃないのかな?
どう考えてる? 近代化工業化の過程で非定住者がそれなりの数いたってどこの国でもありそう
サンカって嘘だったのか・・・
うちの母親の実家は豪農系なんだが、
小さい時に蜂蜜の人だったり、季節労働者達がたくさん泊まりに来てたって言ってたから、
そういう季節性の労働者は存在するのかと思ってたわ
婆さんの時代は牛飼いが牛を連れて来てたって言ってたし
>>135
山は全部権力者が決まってるから
よその村の山で好きなことはできない
山々の権利関係は昔も今もガチガチ 糞田舎の山間に集落作って生活してる人たちの方が謎
落ち延びた平家の子孫って伝説もあるけどほんとそんな感じ
尾瀬の最深部で越冬しながら隠れ済んでたらしいからな
凄い奴らだ
>>289
トゥース春日とか5名くらいが参加した
「アイテム駆使して山林で巡り会え!」企画では
着火剤&焚き火の春日はほぼ役に立たなかった
風で煙が流れたり拡散したりで「なんかあそこらへん
にいる…のかな?」で違う方向に行ったりしていた
少なくとも鏡の反射より役に立ってなかった
しかも薪集めて着火する手間、煙を維持する手間もかかるし
陽の光がないと煙が見えないから夕方夜間明け方は意味がない
(逆に言えば、夜間に木のない斜面で焚き火したら
光で場所を示せる。が夜間は捜索とかしないから効果は薄い) >>134
定住すると家に役人来ちゃうから何にも縛られたくない人がなってる例もあったよ
でも犯罪者の集団だった所もあるしなんらかの理由で家を無くした人もいた
昔家と家系図を中心に家族があったからね 山で暮らす定住しない人って意味なら別にいても不思議じゃないんじゃねーの
仮にある論文が間違ってるからって存在が否定されるとは限らんでしょ
>>134
泥棒村とか売春島とかあるよね
あれも嘘なのかな? >>141
まあ俺が見たことを書いてるだけだから
昔はそういう人たちがいたってだけの話だわ
実際の素性は分からんけどな >>142
昔なんて田畑が耕せればどこでも似たようなもんだろ >>140
季節系の労働者はいるよ、サンガとは関係ない存在だし
つい最近まで東北や北陸の人らは冬に関東や西方面まで働きに出ていたし >>140
〇〇は嘘
これを即信じるやつってマジなんなんだろうな >>152
今もフランスから出稼ぎに来ている元管理人もおるよな >>149
売春島は渡鹿野島とか実際にあるからね
高齢化で寂れただけで最盛期はバブルの頃とかなんでは >>154
この辺が嘘なだけで山奥に住んでた人も戸籍が怪しいジプシーみたいな人もいたにはいたでしょ >>149
売春島はあったよ超有名だった
泥棒村は差別意識から生まれた都市伝説じゃない? 山の中で暮らしてただけの人達だろ
今もただの田舎を秘境だのヤバい部落とか言っちゃうバカいるけど同じノリ
サンカとして統一した文化や国家みたいなのは嘘だけども
彼らのような生活をしていた人間集団がいたのは事実としてある
というかさ、今でこそ仁義を切るなんてヤクザもんがやってたみたいなイメージがあるけど
昔は、例えば木地師とか鋳掛け屋とか旅をする集団は普通に仁義を切って、その所属する所を明らかにしてた
アフリカには石炭を盗んで暮らす集落があるって前にテレビでやってた
セックスして子孫作ってたんだからケンモジよりは上位の存在だぞ
ただの浮浪者や兵役逃れや犯罪犯して逃げてきた人を大げさにしただけだろ
>>159
結局当時はドイツ人などがアイヌ人研究をこぞってやっていたから
そっち方面から注目して貰えやすい様に
アイヌ人感を感じさせる形で色々と話が盛られたんだろうな >>26
今でさえスカリーに追い出されたジョブズの顛末を知ってるやつはほぼいないしな
ありえるわ 子供への脅し文句の山学校てコイツらのことなんだろな
👴「私は普通の日本人です🎌」←20世紀前半まで棲息した昭和の底辺土人
岡本喜八の近頃なぜかチャールストンはヤマタイコクか
いろいろいたんだろうな
土地的に開けた場所にいるとピンと来ないと思うけど、日本の山深いとこというのはほんとに異界だから
そこに適した人達がいたのは頷ける
>>164
日本の山々は全部持ち主がいて
山村の利害関係者がいるのに
流れ者が云々は
ムリムリムリムリかたつむり
中央アルプスである木曽山脈も林業で尾張藩の財政を支えてたわけで 浮浪者というか不定住者的な人たちは実際にいただろう
でもネットで語られる時は、尾ひれはひれ付きすぎて都市伝説化しちゃってる
>>171
南アルプス南部は全部一社の持ち物やと
今、知ったか?
ひとつ賢くなったやろ ちなみにどこだったかの山小屋の管理人は
マタギの末裔なんだよな
一応市街地にも家を持っていて
そっちで妻子が暮らしているらしいけどw
お前らって何歳なんだ?
山窩なんて聞いたこともなかった
>>177
山に所有者がいるという観念は新しい
欧米ですらフランス革命以降
日本でもとりあえず明治維新以降だがそれなりに整備されたのは戦後 石器捏造もだけど第一人者が捏造して全てが嘘くさくなるの日本の文化なのか?
>>161
そういう人はいたと親族から聞いたことがある
戦中から戦後しばらく熊本県球磨川流域で川魚の漁したり、竹細工を作って放浪生活をする一団がいたんだと マタギなんかもサンカの一種じゃね?
共同体に属さない人々で特殊な民族とかではない
>>54
東海パルプってとこの私有地なんだよな
前に登ったときに山頂に社有地って杭立っててビビったわ >>184
バカはお前やろ
南アルプス南部が全部一社の持ち物だと
初めて知りましたと土下座謝罪しとけ まつろわぬ民である山窩は実在したしその痕跡も残ってるし資料も山ほど残ってるけど山窩研究の権威と呼ばれていた人が捏造しまくってイデオロギー闘争に消費してしまったせいで公的に取り扱えなくなった
各地に残った伝承・寓話と一人の狂人の妄想が混ざり合ってしまって山窩が異民族の集団だったのか生活様式が違う日本人だったのかすら判別出来ない
山窩は実在した、実在したが実態は不明のまま安っぽい悲劇として消費されてしまった
アイヌや琉球や被差別部落のように「山窩という可哀想な人達を迫害してきた残酷な日本人!」という語り口でしか語られなくなってしまった
ただ生きていただけ、ただ生きていただけで勝手にイコンに祭り上げられて勝手に存在を否定される
落人の集落なら実在したよ
家や畑を山の裏側に作っていたから近代まで外界から見えなかった
サンカとか99%与太話
青梅の緑眼人の方が余程信憑性がある
>>187
マタギは定住して農耕もしながら狩猟採集の技術も持った人たちでサンカとは別なんじゃないの? 私有地だからこそ定住できずに流れてるんじゃないの?
市民の鬱憤がお上に向けられないように
サンカなる物を作り出し矛先を下に向けさせる。(子供を攫うとかのデマを流す)
>>192
それが間違いである地図提示されたわけだが地図も読めない馬鹿なんだろ? 近所の人が元サンカだな
今でいう戸籍を持たず、
山の中で生活してた感じかな
孤立してたわけでなく、
たまには里に訪れて、
物々交換みたいな事をしてたらしい
この地域では酷くなかったようだけど、
多かれ少なかれ差別されてたようだ
山のことはよく知ってたから、
その点は尊敬されていたようだけど
部落、琉球、アイヌ
どれも縄文の血が濃いよな
九州や東北ほど縄文で
関西(日本史上の首都)に近づくほど弥生になる
山窩も縄文系かもしれん
>>1
朝日じゃん。
疑わしいやらいかがわしいやら。
慰安婦で嘘吐けなくなったら今度は「サンカ」?
ばかじゃないの、こいつら。 >>203
お前バカだろう
谷筋から山頂まで全部社有地なのが理解できてない 私有地って言っても山の奥の奥なんて毎日見回りが来るわけじゃないだろうしな
しかも定期的に移動生活してたら見つかり難いんじゃないかな
そういう人たちがいた方がロマンがあっていいなあ
江戸時代には山賊みたいな集団はいたけど、独自の民族みたいなのは本州にはもう存在してなさそう
やまなんて人の暮らせるとこじゃねえだろ危なすぎンだろ
>>205
九州は南西諸島との交流あった薩摩に縄文系多いだけでほとんど弥生じゃね? >>199
柳田じゃないなんとかいう嘘つきだろサンカ関係は 小学校のクラスメートに謎の貧乏人家庭の子はいたな
ある日突然転校してきて河原の掘っ立て小屋に住んでたりむちゃくちゃ貧乏で親父の職業が竹工だったり
>>187
マタギにはちゃんと年貢を納めていた奴もいたりするので
一緒くたには出来ないんだよな
結局定住しない奴には課税するのが面倒なので
欧州のラマなんかも忌み嫌われた訳なんだけどさ
んで山岳信仰は明治政府が禁じた事で
修験者も今では殆ど居なくなった訳でさ ニヴフも日本に住んでたのに無かったことになってるよな
移動範囲が広くて方言が通じなかっただけでしょ
山でも海でも仕事に季節性あるし結構移動する
>>205
いやいやいやいや琉球とアイヌは全く完全に別だろ
どこが近いんだ? >>212
研究では違った
九州、東北は縄文の血が強いが
関西は弥生の血がとても強い
おそらく弥生の地は都会で選択的に優位なんだろう >>208
東斜面だけな
江戸時代は天領だったんだから国有地みたいなもんだろ
それが民間に払い下げられた特殊な例なのに>>54みたいなこと言っちゃうから馬鹿にされるんだよ >>220
//news.mynavi.jp/article/20121102-a126/ >>169
そう、それが都市伝説でしょ
泥棒だけで共同体が成り立つはずもなく
インドのジャーティで泥棒しか許されないとか効いたことはあるけど 姥捨て山に捨てられたジジババが実を守るために集団生活始めてただけじゃねーか?
>>131
修験道の祖である役小角は飛鳥時代の人だよ 神秘性出そうと盛りすぎたせいで存在そのものを全否定する極端な奴を生み出して
罪だよなぁ
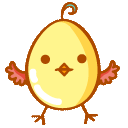
>>208
お前がアホ
勉強しろ 日本で独自言語、独自文化があった民族って
アイヌと琉球だけってこと?
あとは方言レベルの違い?
大陸半島の反乱から逃げてきて日本に馴染めなかった人達とかじゃないの?
>>205
さんかは百姓の次男や三男が食い扶持がないから山で生活してたんだろ >>221
総合研究大 生命科学研究科 遺伝学専攻教授を兼任する国立遺伝学研究所 集団遺伝研究部門の斎藤成也教授、東大大学院 医学系研究科 人類遺伝学専攻分野の徳永勝士教授、東大大学院 理学系研究科・理学部の尾本惠市名誉教授らの研究グループによる研究では
弥生以降の渡来人の分布は北部九州に始まるそうな >>220
戦争で中央が占領されて、負けた側が外側に追いやられていくんだよ
なので沖縄と東北あたりにかつての日本の文化が色濃く残っていると言われている おっ久々の山窩スレか
前回はここ見たぞ
お前ら「サンカ」っていう戸籍を持たない放浪民族が日本にいたって知ってるか
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1600694970/ >>231
そもそも日本は方言の範囲が広すぎる
薩摩や奄美もヨーロッパ基準だと外国語にあたる 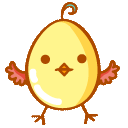
>>228
単純に定住化・社会化なんて人類の歴史からしたら最近のことなのに
それ以前を想像できる感性がなくなってんだよね
私有地ガーとかアホでしかない
法の以前の問題なのに 山ってすぐに顔の周りをスズメバチがブンブンしてきてビクビクしながら歩いた
何が面白いの?
いわゆる「サンカ」って言われる人たちは天保の大飢饉で流民化した人たちが
主たる存在なんじゃないか、って説があるけど
当時行政が把握してる人口が一気にむちゃくちゃ減ってるようだから
亡くなった人が7割8割だとしても数十万が流民化してそのまんま世代を重ねる
ってパターンもあり得るだろうな
つうか大塩平八郎の乱→その理由が天保の大飢饉→サンカに興味が行く
みたいな流れか?
>>225
泥棒を生業にしてたというよりは
村の生活が厳しくなると村人が総出で他の村に盗みにいく習慣みたいなのがあった
昔なら珍しくもなかったんじゃないかな >>225
今だってジンガリとかいるだろ
山賊とか人身売買も含めて >>232
大和朝廷系の日本人が大陸や半島から渡ってきた人でしょ? >>235
近いから血が濃くなるわけじゃないぞ
弥生人の血は都会で有利だから近畿で大きく広がった
www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/story/newsletter/page/7200/ >>227
月山の山の上に神社を作ったりミイラを作ったりしていたのも
修験者といえば修験者なので
そう考えると紀元前から確実にいたよな
それも天狗の様な鼻をしていたり
多神教を広めたりしているのは
アイヌ人というよりインド人や古代ユダヤ人がやってきて
布教していた感じだよな >>131
むしろそいつらがいつから度々熊野に逃げ込む奴がいたんだぞ
山岳信仰は下手したら仏教伝来並みに古い 独自の言語と言うか方言だろ
俺らにとって東北弁が別言語に聞こえるのと同じ
>>250
大陸から渡ってきたら日本語なんて生まれねーでしょ >>233
むしろ今は消えちゃった水上生活者の山エディション。
朝日だけに差別物語に仕立ててやがる。ほんと気色悪い。死ねばいいのに。
東松山を攻め立てる気らしいけど、松山一帯は普通に右なのよな。
四国とか四国近傍の旧家の出の者なら一応知ってるよ「サンカ」とやらを。
サンカは「最後の一人」とやらに至る以前は、
むしろ自分達のテリトリーに侵入してきた人を殺してたでしょ。
そういう事だよ。 >>252
都会で有利?戦争で渡来人が縄文人を駆逐して塗り替えただけじゃないの? 今日、嫌儲で一番平均年齢高いスレ
>>247
初詣行ったらそんなおっさんがオカンジンしてたのギリギリ覚えてる世代、でもほぼ忘れてるわ
この言葉も差別用語なんだろうけど
昔はそういうの身近にいたんだけどなぁ
ほんといなくなったな >>131
熊野神社の出来た時期とか全国に分社が多い事とか考えると相当昔からかなりの人数が全国にいたと思うぞ >>258
もちろんそれもあるだろうけど
それだけだと関西に弥生人が圧倒的に多い理由が説明できない
多分、弥生人は集団生活が得意なんだろう >>252
鬼界カルデラのアカホヤ火山灰の分布見れば一旦九州から関東近くまで人が住めなくなったっぽいからな
そこに入り込んだのが弥生系渡来人ってだけでしょ >>262
人は住めないが渡来人は住めたとかどんな妄想だよw 大学生の頃話題の書籍ってことで読んだけど
アホだったんでよくわからないまま放置
50年ほど前なら中国の食人文化を語った方が現実的だわ
>>261
その当時にそこに住んでいた縄文人をほとんど殺すか島流ししてたりして >>262
鬼界カルデラは7300年前
弥生人の流入は2400年前
かなり違う、多分弥生人は春秋戦国関連だろう
遺伝子的には東北、九州が縄文で
関西が弥生 >>261
関西に多いのは琵琶湖があり稲作に適してる土地だからだよ
始め弥生人は九州を中心に生活してたが阿蘇の噴火で稲作に不向きな土地だとわかって
どんどん近畿に移住してきた >>270
動物殺すのがマタギ。
人間殺すのがサンカ。(野人て呼んでたけど) >>259
オカンジンって北関東の呼び方じゃないのか?
瀬戸内あたりはほいととかへんどって呼ぶんじゃないか? アイヌ>>>沖縄>本土ジャップの順番に遺伝子は近いらしいが
言語はアイヌ語≠日本語・琉球語なんだよな
この辺が謎でありロマンである
2071年
50年前まで「ケンモメン」という独自の言語を使ってネットを渡り歩く謎の民族が日本に居たらしい
>>261
狩猟採取のマタギより農業をやってる百姓連中のほうが人口は爆発的に増えるだろ >>54
北海道だが逃げ出した中国人強制連行被害者が戦後も10年以上誰にも見つからず暮らせてたんだし
大昔ならあり得る話やろ >>265
自然環境が回復してきたころに渡来人が入り込んだってのがそんなにおかしいか? >>276
畿内に渡来人が来て分断されたってことじゃないかな? >>276
多分、縄文人は狩猟民族だから集団生活に向いていない可能性がある >>276
九州北部から弥生人が侵入して
九州南部と本州のグループに別れた
九州の縄文系は鹿児島や琉球へ逃れ、
本州の縄文人も弥生人が入植すると次第に東北へ追いやられていった >>276
中央を駆逐されて外側に追いやられたからだよ >>257
行政批判の記事は行政調査新聞というとこの引用であって朝日関係ないだろ 江戸時代に食うものないから新田開発しまくったせいで
それまで誰も住んでない山の奥まで集落ができる
当たり前だけど便利なところは中世までに人が住んで田畑作ってるので
不便で猫の額ほどの人里離れた僻地にそういうのができる
これも当然だけど自分の土地がもともとあった人は便利な土地にいればいいわけなので
そういう不便な僻地は貧乏人が行く
すると山の中に貧乏集落が点在するようになる
作物だけ育てても厳しいから売る用に山菜取ったり草鞋作ったりする
山の中だけで生活完結できないし定期的に外の血が交じらないとダメなのでちょくちょく里に下りる
じゃあ里の人は「うわ、山の中の貧乏人!えんがちょ!」するから差別される
買い物はともかく嫁もそういう貧乏僻地からもらわざるを得ず余計差別される
こんなイメージ
でもドングリ食べてた時代に春秋戦国時代って
凄いよな
>>284-287
マジかー んじゃ結構長い時間かけて移動したんだな >>16
狩猟をしたり鍛治や木工(お椀とか作る人)やってたのが山窩なんでねーの?
定住しないで移動しながら生活してるので
そういうわけで、昭和初期くらいまできちんとした戸籍がない人とかいた
独自言語使ってたみたいな話は聞いたことないな >>15
うちはその人達にアレイ提供してた家だから、
言い伝え残ってる。
水軍生活のまま昭和に至っちゃった人たち。
もとは孤島の島民だったりしたけど、船暮らしの方がいいって事で群れた。
日本語は通じたし、船の中から子供は登校して、
親は仲仕や塩とか運ぶ荷役やってたんだって。
ほんと朝日って気色悪い。 >>295
その割には古代史にあんまり痕跡無いよな
アイヌと本格的にぶつかるのも東北に手を出し始めた平安時代初期なわけだし 山窩と呼ばれた人たちがいたことと、山窩について話をいろいろ盛ったのは別のことだからな
>>290
放火魔が「サンカ」に触ってることに変りは無い。
怖いわ、ほんと。 >>302
これを混同して頭から否定したがる頭のおかしい集団が居るよな 山に住んでる人たちが冬場は人里に降りてきて経済活動に加わったとか
べつにそんな自然なことじゃないの?
縄文人=蝦夷=穢多=同和 なんじゃないかと思ってる
これが一番しっくりくる
>>304
早いとこ強制連行報じた産経新聞にも謝罪させてこいよw 独自の言語は嘘
独自の単語(ほぼ本州アイヌ語由来)は今も東北マタギが使ってる
今は登山客や観光客で賑わう北アルプスの黒部山域には
昭和まで「山賊」と呼ばれる者達がおってな・・・
>>298
追加
そのひとたちの仕事が港湾労働だから、
船で港から港へ即行けた方が好都合だったの。
親の船から子供は公立学校に通った。
元は孤島住みの冷や飯くい側の水軍の雑兵の末裔みたいなひとたち。 >>307
蝦夷俘囚説は部落解放同盟が否定的見解をだしてる >>308
なんで産経に私が関わらなきゃいけない?。
朝日の慰安婦うそ吐きがほんと、
怖かったんだから。
うちは古い家なんで慰安婦の話だってきちんと伝わってるわ。
朝鮮半島から日本にブラック就職してきた朝鮮人のことも。
嘘はきめ。死んじまいな。 瀬戸内海の水上生活者を家船というが、沖浦は彼らを村上水軍の残党の末裔か?と位置づけていたな
俺の地元の島嶼部の被差別部落はそこにまつられた神社や伝承から、その可能性は高いと思っている
それで島嶼部や沿岸に定住しなかったものが家船となったのではないか?
彼らは昭和60年ころまでは瀬戸内海ではあたりまえにいて、港に止めた船から子どもたちが学校に通っていた
大分県出身の曽祖父まで家船で生活していたと言う知人から話を聞いたこともある
ケンモジにそんな自然の中でお生きていけるような生命力はない
>>307
穢多は仏教伝来から始まった話ってのが有力なんじゃないの >>275
千葉だ
オカンジンて言葉はギョッとするものがあるんだけど、他の地域の人にはないみたいだな
瀬戸内はホイトとかヘンドでギョッとするんだろうな… 義経逃亡に付き従ってたのはこういうマツロワヌタミだったなんて聞いたな
昔嫌儲で1001のAAの雪さんがサンカという設定なのを知ってる嫌儲民は少ない
竹細工とか売ってたわけだからある程度の日本語の交渉も話せそうだけどな
これから経済終わって荒れた世になったら、サンカみたいな人が増えるかもな
>>321
オカンジンは勧進からきた言葉だろうから托鉢坊主みたいな乞食生活をそう呼んでた話が始まりなんじゃないかね >>220
琉球は古代日本語を話す南九州人が平安時代に南へ下って征服しただけ
縄文時代からの言語はアイヌだけ >>327
だろうな
歌舞伎の勧進帳を知って、「!?」てなったわ子供のころ >>317
昔は干潟に住んでる人は田船を使って陸地へ移動してたし
護岸整備とかがされるまでは渡し船もあったっていうしな
そういう意味での水上生活は珍しくなかったんでは >>320
伊勢と出雲の神社戦争で破れた出雲側神官等が被差別階級に落ちたり
南北朝の後で負けた南朝側に付いた集落や家系等が
被差別階級に落ちたなんてのもあるんで
一筋縄にはいかないんだよ >>72
さらに他地域のサンカ同士の交流なんか地理的にも不可能で、まずありえない。山間部の住民は炭やら籠細工やら砂鉄やらを平野の民に売って(物々交換して)生活してるわけで、独自の言語を持つメリットが全くない。 漫画版風の谷のナウシカの森の人みたいだな いや虫使いのが近いか
>>257
>東松山を攻め立てる気らしいけど、松山一帯は普通に右なのよな。
>四国とか四国近傍の旧家の出の者なら一応知ってるよ「サンカ」とやらを。
なんか東松山が愛媛県にあると思ってそうww >>15
場所書かないと話のすり合わせができないだろ?
これだから年寄りは >>331
その辺は「非人」の方なんじゃないの
村とか町とかに正式に籍置けない人は皆非人だったんでしょ? サンカのスレ定期的に立つよな
で毎回民俗学者かなんかの書籍がすすめられる
Wikipediaのページが熱いのんな!後で読もう
>>15
つげ義春の漫画の子供の頃の体験に出てきたな、戦前戦後くらいまではいたらしい >>339
暇つぶしの雑学妄想のネタとしてはかなり面白いからなw >>7
最近、反日リベラルがアイヌとかサンカとか持ち出してきて日本をめちゃくちゃにしようとしてる >>334
愛媛の東のことじゃないの?
所詮、四国にいたのと同類でしょ。
その人らは殺すんだよ、人間を。
四国ホラーの元ネタだよ、その人たち。 ほうよ
全部フィクション
全部朝鮮部落製フィクション
山窩コネクション!!
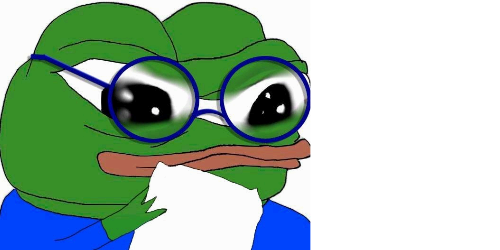
おれはカムイ伝出始めって知ったわ
両刃の短刀とかなんか別の人種が源流に有るんだと思う。
>>15
大昔だけど俺が子供だったころは木の上に1人で住んでる友達いたぞ
一緒に川で釣りしたり洞窟探検したりして楽しかったな 空海が高野山開いたのも山の人との交流があったからとか
・結婚、就職など一般社会に背を向けている
・めったに人前に姿を見せない
・極度の貧困
・独特の食文化を持つ
これケンモメンでは……

俺ウメガイ持ってるわ 「サンカの真実 三角寛の虚構」
この本が読みたいけど絶版なんだよなぁ
>>353
それ金持ちの子どもだろ
田舎にツリーハウス買ってもらって妖怪のふりして遊んでたんだよ >>351
もっと怖い。
四国エディションの「サンカ」は言葉もあんまし通じないし、けっこうな集落も作ったらしい。
(場所も知ってるけど今は書かない)
その人ら、行政(明治政府の頃とかから)が訊ねていったりして、
「面倒臭い」となったら殺して逃げるから、
誰かを殺して逃げるたんびにちりぢりになってコミュニティーが縮小してゆく。
ラスト一人とかになるのは当たり前。殺しをやるから。
こういった流れを「里の者が迫害した所為」「差別」と主格転倒させて、
キーキーと日本人を断罪するのが朝日新聞。
犯罪者集団だわ、朝日新聞て。 ただの平家の落ち武者末裔が
誰もこない山奥でひっそり生きてただけの話
たいてい炭焼き
>>359
非人って呼び方の方は仏教では被差別的な要素もないし仏教関係なく昔から存在した言葉なんじゃないかと思ううんだが
穢多はいかにも仏教の影響を受けた価値観だよなあ >>26
50年前100年前のことですらあやふやなのに1000年後の奴らが安倍のことなんか知る訳ない >>370
エタヒニンは天皇制と関係してるから神道でしょ
仏教には差別思想はない >>375
天皇制が仏教から切り離されたのは明治以降でしょ 今でも日本でハングルという謎言語使ってるケンモメンという存在がいるんだが
>>15
晴海のあれが沖浦光則みたいな名前の学者の本で読んだ家船だと思ってワクワクしたけど違った >>15
この書き込みもだがこれについてるレスも面白い
つかさらっと宮本輝が出てくるのがすげえ 友達がお婆さんに子供の頃なにしてたのかを聞いたら、山から山を駆け回ってたみたいな事を言われたらしい
親方さんは○○○にいるとも話してたんだとよ
昔は寺単位のコミュニティで管理されてて、生れ在所以外に移動はできなかったから、逃亡農民は都市に逃げて無宿人になるか山に逃げてサンカ的な生活してたんだよ
終戦直後位まではこういう人がわりといたとか年寄りは言ってるな
だから別に謎文字や謎言葉を使ってた訳ではなく、単に季節で移動してたそういう事情の人達なんだよ
200年ぐらいたったら「こどおじ」っていう家の民みたいなのも珍獣扱いされそう
>>148
幅広い意味ではマタギや川漁師、水上民、竹細工、砂金とりなんかをして
一般の社会生活なんかから離れた生活を送る人たちがサンカなんだろうけど
サンカっていう共通の文化を持つ集団が全国的にいたかというとそんなわけじゃないということなんだろうな
中にはサンカを自認する人もいれば本人達にそんな意識はないけど生活様式が行政用語や警察用語でいうサンカに当てはまる人はたくさん居ただろう
今でもサンカ的な生活をしてる人はいるだろうけど
現代だと何らかの労働して生産性のある人生を送ると
戸籍と住民票もって健康保険みたいな行政サービス受けたり選挙権とかの国民としての権利の行使や納税や教育なんかの義務を果たして国家の枠組みにハマらざるを得ないし
ホームレスみたいなのは居ても純粋な漂白民と言うのは存在が難しいんじゃないの 日本の民俗学とかいう明確なソースもない妄想垂れ流しの典型例みたいな三角寛の小説設定
>>340
淡々と複数視点の定義を書いているだけで
エンターテイメントにはなってないと思うぞ >>343
知能指数本当低そうで笑えない
日本を常に神格化してないと気が狂うのか >>392
サンカとかをやたらを否定したがる人は何が目的なのかと思ってたけどネトウヨだとわかったのですっきりした 文系学問は政治的傾向が強いよな
国体を否定するような事実は仮に研究結果として明確に証明されていても黙殺、あるいは捏造が状態化
もはや学問とは言えん
>>108
関所が張り巡らされてたらそうだが実際にはそうでもないだろ だってかさ地蔵のお爺さんだって冬は何もできないから町に行って不器用ながら作ってみた笠を売りに行ったんだろ?
>>401
昔の農民は出稼ぎの概念がないから、農閑期は縄を編んだり蓑笠作ったりして生活費稼いでたんだよ
笠地蔵のじーさんは別にサンカ的な生活してたわけじゃなくありふれた農民だよ 三角寛の雑司が谷の家が料亭になってたんだが2019年に建て替えのため閉店してた
>>108
そもそものめちゃくそ厳しい関所のイメージが嘘だし 秋田の阿仁マタギは冬になると山梨の甲斐駒まで出張してた記録が残ってる
サンカとは違うんだが謎のカルト的な集団
使用中止になったトンネルに洗濯機まで持ち込んで複数家族で住み着いた連中なら居たな
警察の追い出されてトンネルの入り口は完全に塞がれる事になったが
彼らは何だったのか今でもわからない
発電機持っていたり移動の車あったり燃料買っていたり生活は円ベース
日本語も通じているが子供は学校に通っていない謎の集団
>>15
大阪市大正区とかは昭和の時代そんな感じやったらしいな こいつら普通に日本語喋れて里で物々交換や商売やったりしてたらしいじゃん
公園にテント張って住む一族がいた!っていうのと変わらんw
よくある伝奇ものエロゲと思ってたら山窩が絡んでたことがあった
出来としてはしょうもなかった
>>233
農業には労働者が必要なので二男三男は貴重な奴隷 昔は五木寛之を読んで山窩に憧れたものだがほとんど嘘だったんだよなあ
三角寛の創作小説みたいなもんだろ
ウメガイだって伝聞とかレプリカだけで実物が残ってないんだし
>>15
普通に興味深い話しだな
ジジモメンの年齢は? >>419
その割には凄く家族内での風当たり強い描写多い気がする
貴重な奴隷ってまた解釈に困る言葉だなw >>410
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003023837
不就学学齢児童生徒調査って統計があって1年以上居所不明者数ってのが326人もいるんだよな
この子たちの親がどんな人なのか気になるよな >>403
北国農民の出稼ぎって近代以降のものなのか?
確かに江戸時代までは農民の移動の自由は制限されてただろうな
それも幕末には相当怪しくなってたろうけど そういや昔は色々な人がいたよな
全国を旅してるサーカス団とか旅芸人の一座とか
そういう人たち見なくなったけどどうなったんだろうな
広島の実家がサンカと取引があったが
物々交換や棚田の石垣修理などの農業土木をやって米を山村農家から受け取っていた
独自の言語云々は聞いたことが無い
田舎に出入りしていたサンカは2グループあって
1グループは飢饉の際に山に逃げ込んだ逃散農民の子孫で
もう一グループは石見銀山など中国地方で盛んだった鉱山からの逃亡人夫と
鉱山町の逃亡女郎が山に逃げ込んだグループだった
どっちも広島市内での戦後復興の日雇い仕事需要が増えたあたりで消えた
>>426
昔は北海道あたりに出稼ぎに行ってた
江戸時代は藩の中でやりくりじゃない >>332
全くメリットはなくても存在した猟師言葉とかもあるからなあ >>426
俺らが想像する、農閑期だけ土方仕事しに出稼ぎするようなのは明治以降だね
江戸時代の道路普請は基本地元の農家が徴発されたり、納税の代わりに道路普請や伝馬してた層がやるから、冬のバイト的な仕事がないのよ
杜氏みたいな職人や行商は別だけど ( ゚Д゚)「昔はたくさんいたんだよ」
(´・ω・)「何が起きたんだい?共産政権を目指す山奥ソムリエのおいらは語る」
( ゚Д゚)「自動車文化は逆にさ、地域の小さなネットワークを破壊して都市と田舎を結び付けた」
(´・ω・)「隅っこで楽しく暮らしてる人たちを殺したんだね。殺人政党の自民党」
( ゚Д゚)「そう。なんにでもランキングがつけて他人を笑うようになった」
(´・ω・)「殺人の自民党らしいね」
( ゚Д゚)「あいつら自民党がいるから日本がだめになるんだ」
昭和の30年代に消えたらしいけど
まだ最後の世代
親の話を聞いてる子や孫の世代はいるはず
聞き取りをするなら最後のチャンスくらいじゃないか
あと10年もすれば第1世代はもう消えてるだろう
>>432
昔は木がとんでもなく価値があったから、山の人間の方が金持ちとか普通にあったし開発もされてたのよ
今でもすごい山奥にお城みたいな屋敷を構えてる家がそれ
ただそれでも山で生きていた人はたくさんいたのよ サンカは実在したよ
ただし世間に広まってるサンカ伝説はいわゆる第一人者がねつ造しまくったっていうだけ
>>15だけどメッチャレスついててビビるわ
和歌山出身の40代半ば
ガキの頃過ぎて季節は覚えてないけど、河原で遊ぶのは初夏から秋にかけての頃で1ヶ月もないぐらいな
学校には来てなかったけど、兄はやたらと頭が良かった記憶がある。妹の記憶は全く無い >>431
生活が違えば生活の中で必要になる名詞も変わってくるからな >>15
ハシケじゃないかな
小学生の頃に仲良くなった男の子がそれだった
何度か船に遊びに行ったけど、その子の母親に「もうここにはきたらだめよ」とやんわり言われ、その時に茶色い角砂糖もらった記憶がある
その子は学校に通ってなくて、少ししたら船ごとどこかに移動してもう出会うことはなくなった
元気にしてるかな?昭和20年頃だったから生きてたら80歳は超えているはず 黒部の山賊って本が、サンカではないけどサンカ的な生活してた人の話だから興味ある人は読んでみるといいかも
実際は山賊ではないし、麓に家も家族もいる人たちだけど、年単位で山で生活してた人の話が載ってる
サンカ的な人も、実際はこの山賊みたいな生活してた人がおおかったんじゃないかな
>>443
昔は水上生活してる貧困層が普通にいた
ってブラタモリでタモリが言ってた >>236
追いやられたっていうのはおかしい
むしろ隼人とか蝦夷は中央に集団移住させられたりしてる
地方の方が古い文化が残っているとかいうのも眉唾で未だに蝸牛考あたりの古い周圏論的な考え方に囚われてて、実際には関西にも古い文化は残っていたりする >>445
いや猟師言葉はまた別だよ
もちろんそういう普通の日本語に無い言葉とかもあるが
ある言葉でも別の呼び方をする >>1
昔は戦に負けた平家とか新田とかが散所に閉じ込められたんだ
被差別部落のことだよ 前に沖浦和光っていう人が書いた「幻の漂泊民・サンカ」って本読んだけど
三角寛とかのフィクションによるイメージがついた部分が大きいってちゃんと記述しながらも
本当に山窩ってのがいたのかどうかを少ない資料とか探し回って自分で調査してて面白かったぞ
>>315
山岳ガイド、猟友会、山小屋管理
色々だね。 >>443
戦後から昭和中期くらいまでは船上生活者結構いたらしいけど法規制されて消えたってなんかで読んだな。
60代70代くらいの文学作品とかにはわりと出てくる。船で売春してるやつとか塩運んでるおじさんとか。
こち亀にも出てきた気がする。 1950〜60年代にもうその辺の地元に溶け込んでほぼいなくなったらしいし
実際にそれっぽいの見たことあったって書き込んでる奴は何歳だよ…
>>460
船上生活者も別に貧しいって事も無かったらしいよね >>451
マジか~考えを改めたいので、具体的に中央に残ってる文化があれば教えてほしいな うちの近所では道の街路樹の影とかで
網籠編んでる親父が作業して座ってたり
針金で何か道具を作ってる親父がいたり
とにかく歩道にいきなりいるんだよね
こういうのってユダヤ人の兵役明けのバックパッカーがやりがちだけど
うちの近所で時々見るのは
日本人のジジイだけど地下足袋履いてたりしてるし
日本人の親父だけどhoboな感じで楽しそう
ああいうのも流れ者じゃないかなって思う
>>458
なんか夢があるじゃん
この狭い島国でも戸籍を持たず狩猟や略奪をメインとした集団がいて
独自の言語体系を築いてるとかワクワクする 日本でサンカに唯一近い?
九州五家荘の落人集落でさえ、飢饉の時は、肥後藩に助け求めてたらしいし、ロマンないよなぁ
>>280
それが集団を形成して血が濃くならずに子々孫々世代を重ねて暮らしていけるのか? >>15
水上生活者とか本とか映画でしか見たことないわ
宮本常一の本とかそれこそ上がってる「泥の河」とか ケンモメンが山窩叩いててビビるわ
弱者よりなのに
より弱者を叩くお前らもまたジャップってことか
>>7
ゴッドハンドの旧石器みたいに三角のせいで
知能低いやつがお気楽に全否定するジャンルに
成り下がったのは残念。 神戸はポーアイ博の頃まで艀に住んでる人は普通にいた
その後は市営住宅に入ったんちゃうかな
単なる山型ホームレスだろ
俺が子供の頃(1970年代)にはギリ、スクラップのバスの中で生活してる人いたわ
生活保護なんて無かったんよね、昔から
>>468
五家庄は普通に里だよ
でも宮崎県の椎葉と熊本の五家庄の間の国見岳あたりはほんとに人里の気配のないエリアがあるんだよね
あの辺はなかなかロマンがある >>15
こち亀にあったな
昭和の頃の友人の家が停留してる船だったって >>70
ロマは日本の被差別集団みたいに昔は法皇の許しを得て巡礼をしていると称してさすらってた。
後に16世紀ぐらいから処罰されたり、奴隷のように軍事や労働に徴発されるようになった。
20世紀に入るとナチスドイツがユダヤ人と同じ様にに絶滅させようとした。 独自の言語ってのも知的障害に由来していた可能性が大きい
サンカというのは山の中で移動する遊牧民
今の日本には遊牧民がいないが、海外には遊牧民がいる
ぶっちゃけ山には生活していけるほどの食物は無い
めちゃくちゃ寒いし
盗賊でもやらなきゃ流浪はほぼ無理
50年前までいたとかいうなら、資料残って無さ過ぎだろ
水上生活者は残ってるのに
>>321
うちのオカン広島出身だったけど
怒ると「お前はほいとじゃ」とよく言ってたわ
そういう意味だったのか >>485
横浜あたりの水上生活者は会社員だからな
社宅として船の居住部分が使われてた感じ >>446
ハシゲさんと関係あったりするのかな
いろいろ妄想が膨らむな >>488
艀と書く
大型船が着岸しないで荷物の積み下ろしするのに岸壁と船を往復して荷物を運ぶ動力の無い輸送船のこと >>461
山賊ってのは、里の人たちの噂でそう呼ばれていただけで
実際は猟師や釣り師で山の民みたいな人たちだったからね。 >>486
東北の福島だけどほいどって言われてたな乞食やホームレスを指して >>490
テンカラなんてのもそういう人たちの釣法なのかなと思ったりする >>483
牛や羊や馬とかなんて飼ってないしどこが遊牧民だよ >>483
頭悪そう
他国に「走った」百姓が歓迎されるのに何いってんの?
ゾゥとするほどノータリン白痴しかいないな
そもそも明治の植林までほとんどハゲ山
生い茂ってるところはほぼ藩の禁足地
なのにどこにどう存在し得るのかと
そもそもサンカの記述なんて戦後の白痴ボンクラが書いた記述が一番多い、そして本当に僅かに明治に出てくる(的が浜くらい)レベルなのに、まともな頭してるまともな人間からすれば失笑モンという
逃散った百姓でも歓迎され、賤民扱いのエッタ非人なんて「独占業務」があるのに逃げるとしたら犯罪者
江戸の与力以下の捜査力舐めすぎから全く知らん&明治の植林さえも知らない間抜けの妄想に21世紀にもなって踊らされてるってもう死んだ方がいいよ馬鹿すぎでしょ >>482
お前が知的障害抱えてるようにしか見えないわ…w
エッタや非人どころか全ての職業に訛りや独特の言葉あるし、江戸時代なんかその最盛期もいいとこなのにその発想がもう「戦後の白痴ノータリン」そのものという >>435
ここの馬鹿達の言う「昔の船上生活者」だのがどう考えても明治中頃からの極々一時期と言う間抜けさ
江戸時代はどうしてたって?
地域の年寄だのが100%許さない オッペケ Sr11-YVOl
なんやこの知的障害?
>>477
割とそれが正解よ
もし存在したとしても極めて稀に存在した明治の貧困スラムの一形態に過ぎない
現代のごく稀にいるであろう車中ホームレス見て100年後の人間が「2020年前後の人間は車が家だった!」みたいな統失レベルの妄想よ
サンカなんてGONだのの自称アングラ系のアホ本見てきた層しか信じてないんだよね
戦後生まれの糞レベルの学者で稀にいるかもだが、まっ、馬鹿のご挨拶だね >>498
そのしょーもないレス見て思わない?
圧倒的にガイジ超えの白痴が自分自身ってさ?笑
0.0000001ミリでも反論してみろよ腐れノータリン白痴よ 笑
コンドーム破れたせいで生まれた感じがするよお前 笑 30年くらい前までは公園や街中でホームレスのおっちゃん達をしょっちゅう見たから生まれる前の時代ならそんな人もいたのかもしれんなぁくらいには思えるな
>>490
てっきりヒャッハー的な存在やと思ってたわ 江戸期における与力における捜査力というのがいかほどのものなのか
ちょっと気になるんだけど、なんか文献とかある?
https://i.imgur.com/EjZniql.jpg
まぁこんな明治の賤民番付に等しいもん含めて「庶民の賤民視」の中でサンカみたいなもんは入ってるの見たこともなく
もっと極レアで神秘的なんですよ的なものたとえあったとしても異人見つけたら宿に押し掛けるレベルの好奇心の持ち主達がほっとくはずもなく、実在すれば噂話与太話が残らないはずもなく
で、ここのサンカ信じてる白痴はほうかい屋とかわかるのかな?笑
少なくともこの番付の前頭上位まではほぼ江戸期のエッタ非人の支配下だけど 実態は現代のホームレスと同じで後天的にサンカになるじょ
>>504
与力は警察署長的なもんだけどな
それでも家老や騎士陣にはない捜査上の特権もあったわけで
ま、それくらい知っとかないと「存在しえないサンカ」信じちゃうよなぁ 笑
江戸期のエッタ非人でも知ってるわけで 笑 >>504
岡っ引はいわゆる被差別民だったとは聞くね
鳥取、島根のチョウリンボウ拷問専門の警察も被差別民
鳥取県警本部に拷問用具が残ってる サンカは三角寛の小説だと数時間で新宿から小仏峠まで走りきったりするからなあ
これソース読んだけど可愛そうというか職員ヤバいだろ
>>510
警察権者を被差別民ってのも笑えるけどな
まぁ今のポリへの見方と変わらん程度だろう
喜田の言うようにエタ非人なんてコンビニにたむろする土方を見るレベルだったのに煽られて黒人奴隷レベルに扱われるようになってるのが笑える 今時珍しいくらい質の高いスレだな
こう言う話題はアフィも食いつかないし久しぶりに嫌儲の底力を見た
>>513
そいつしらんが八王子なんてそもそも極めて重要な土地なのにエタ非人の支配下でもない輩がウロウロできると思ってそうで馬鹿じゃん
サンカ自体で白痴の自己紹介してくれてるけど中学程度の教育受けてないんじゃないのその人? サンカより三角寛の怪人ぶりのほうが興味深いわ
柳田が死んでから絡むのとか嫌儲イズムすら感じる
今ソース読んだが「サンカの末裔」ってのがもう「ムー」レベルの間抜けさで…笑
まだムーの方がマシかもねいろいろと 笑
ああ、この三角寛とかいうドボンクラがサンカの与太話の発祥みたいなもんなのね
角袖の刑事=デカみたいな造語が山ほどできてる明治+江戸期を全く知らない層というオチ
そしてやっぱり的が浜 笑
続けてwikipedia山窩を見るも、共感性羞恥心感じるレベルでお寒い 笑
>箕を生産することでも知られ
笑
江戸時代に箕の99.9999%を作ってたのが誰かさえ知ってりゃもう論破なのになぁ
白痴しかいねえなほんと
>>240
そこらへん単一民族国家神話と絡まって言語学より政治的スタンスの問題になってくるから糞
琉球語非日本語論者でも八重山や宮古語を琉球語方言にくくるかくくらないかとかあるし 三角寛って人の創作によるものとされてる部分がかなりあって
昔サンカについて調べると唯一の出典がこいつだけってかなりあった
あったかどうか別として水木しげるみたいなもんだと思ったら納得できた
先住民やで
彼らこそほんまの『日本人』。
ルーツは渡来人との戦争に負けて山に追いやられた縄文人の子孫。
歴代の日本政権に服従せず、伝統的縄文テリトリーである『山』『森』を住処とする。
『サンカ文字』という独自の文字を持つ(神代文字の起源)。
米国で言う『インディアン』やな
なんか関東でも奥多摩だの秩父だのの
関東山地にはかなり最近まで居住実態があったとか言ってるけど
ここ十年程度だが昔から所沢狭山入間地域に根ざして居る人と縁ができてからは
所謂部落差別的な実態はあったってのは経験談から聞いてみるにわかるんだけどサンカなんて聞いた事もねえよ
もう80になる婆様が小さい頃はあそこの川の向こうは
昔部落だったから容易に近づくなみたいな話を小さい頃にされて
実際村社会で実態としてあったってのは聞いた
そっから推測するに狭山事件とかの背景も浮かび上がってくるから
歴史的に何かしら交差する部分を見つける事ができるんだけど
おとぎ話的な山を住処にしてて箕を作るのを生業にしてて云々なんてまるで聞いた事もない
それまでは直接その地域の人間との交流がなかったから
サンカとかウィキペディアで見てそんなんあったんか程度に感じてたけど
創作だって最近検証されるようになってきたら
ああ水木しげるの妖怪みたいなもんかって思っておとぎ話程度のものって感覚になったしな
>>1
サンカではなくただの部落やろ
>>509
与力は室町時代の足軽頭、江戸時代の同心頭
署長ではないし騎士などいない
武士は時代小説のネタ いわゆる修験僧だの山賊だのって
局所的にごく限られた範囲でその時代時代で生活拠点としていたのは居た事はあるだろうが
民俗学的に全く異質の民族が山を中心に存在していて
しかも最近まで存在していて急に消えたみたいなのってほぼ眉唾
アイヌや琉球王国みたいにいちいち検証するまでもなく
多数の文化や痕跡や資料が残っているのならともかく
洞窟に根ざして工芸品を作って里の民と交流し
あえて山にこもって生活することを選んだって適当に作ったお話としか思えん
ソース読んだら糞胸糞記事だった
東松山糞すぎるだろ
>>1
読みにくい文章だな
ほんとにプロの物書きか? いかりや長介がサンカの末裔って聞いたがな
ドリフターズはサンカの集まりとか
>>359
士農工商が大まかな職業区分で
どれにも当てはまらない役者や芸術家、神官とかそれこそ下級貴族とか今で言うその他の項目が非人だったと言う考え方はあるな
武士や百姓もその中で地位や貧富の差はあるし
非人も一律じゃなく稼いでたり人気者ものいれば社会的に尊敬される人もいただろう
ただ生産性をもった士農工商に比べて
無形のモノを扱うとらえどころない職業には見られてたかも 偉そうにベラベラベラベライキってるくせにサンカの本で有名な三角寛も知らねえで今調べて分かった気になってて草
ガチの汚言症の知的障害やんけこいつw
なんでこうも盛り上がるのかと言うとロマンなんだね
山の中でどうやって暮らすのかとかそれこそポツンと一軒家が高視聴率を叩きだす所以でもある
それは今の生活に限界を感じてて逃げ出したいと常日頃思ってるからなんだよ
狩猟採集だけで生活できたのは遠い昔の話なんだけどね
要するに漂泊タイプの奴ってだけだろ
今はホームレスや簡易宿泊所に居るはず。街の方が楽しいし日雇い仕事もあるしな
>>57
俺もこれ思い出したけどこれとは違うんじゃね? >>536
白痴馬鹿しか読まんだろそんな本…w
人生の無駄遣い、精神に異常あるかよほどの脳味噌足りてないバカしか読まないだろうに可哀想
先祖はチョンかエタ非人じゃねお前のとこ?笑 >>531
修験は何かに所属してる(せざるを得ない)し、山賊なんてむしろ刀持ってる奴らの恰好の餌食定期 >>464
天竜川とか木曽川なんかがそうだけど大きい川は自動車輸送が発達するまでは運河みたいに使われてて遺構が今でも残ってるし
テンカラの和竿なんかも川漁師が仕事に使ってたものが人気をよんで和竿職人になってたりするし
海運ほどのハデさはなくても稼ぐ人はそれなりに居たんだろうな
季節で移動するようなパターンなら漁師とかかもなあ >>402
それはヒンズーカースト制度だろ
仏陀はそれを否定したからヒンズーからは悪魔扱いされている >>529
ああ、馬鹿なの?
騎士なんて「徒士」の対義語で普通に使われるし、与力なんて警察署長レベルで「よほどのことがないと出てこない」って意義ね
いうて県警本部長とかか、わかる奴にはわかるだろうに このさんかの嘘作った人すげえなあ
小卒なのに日大卒と嘘ついて嘘のサンカ論文で博士号まで取ってるとか
>>538
ここでいう「サンカ」とイメージされる集団は
一家や血族、あるいはもう少し大きい集団で非定住生活していたわけで
そういう歴史用語でいう「浮浪」とはまた違う >>547
実際にそんな賤民がいたらエセ同和だのがほっとくはずもないンだわ それでも真実だぞーー!ってジャップは未だ言ってるし
影響力すげーな
>>56
東京DEEP案内でも取り上げられてたな
あんなのかま令和になっても残ってたとか信じられんわ 集団が日本の山奥を放浪なんてとても無理
まず水はどうすんの
サンカ伝説ってどの地域にあったとか特定されてるん?
>>111
山の中で生活してた人達が交易のために下界に降りたら下界の人が勝手に想像して
山の人もそっちの方が箔がついて交易しやすいから次第に自称しだす
って感じありそう 半年くらい根拠地でザルだのカゴだの作って半年は農村を行商して歩きメンテナンスを請け負ったりもするようなのが実態だというけど
ルーツも独自の民族なんてのは大嘘でせいぜい江戸後期の逃散農民くらいだとか
昔の有名な裏ビデ女優の田口ゆかりがそういう出身らしい
>東京都大田区羽田の海老取川の船上生活者の家庭に生まれる。
>物心つく前に母親が家出、3歳の時、父が事故死、生活保護を受けながら祖母と少女時代を過ごす。
>14歳でキャバレーで働き、学校にもほとんど行かず不良の仲間入りをしてシンナー、売春などで中学三年の時、群馬県榛名の女子少年院に一年半入る。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%8F%A3%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A >>559
ザルだのカゴだの「白米も食えない」百姓が買うって?笑
江戸時代の百姓は白米も食えなかった
↓
白米食えないけどザルや麛は買う
馬鹿なの?笑
都会部じゃ籠だのザルだのこそ「エタ非人の特権」だし、田舎じゃ味噌から飴から「ザルやカゴ」まで自ら作ってるわ >>560
アンパンかましすぎて何もわかってないんだろ定期だろ…w
羽田は歴とした曰くが多く残る土地なのに
明治~昭和の貧困スラムをあたかも江戸時代から続いてる風な風潮ってエセ同和や左翼の手だよな
白痴はコロリと騙されちゃう…w エスペラント語みたいなもんかな
ジャップ連呼もその頃からやってそうだよね
>>565
日本においてはそれが「問題」とされたのは明治になってからなんだがな >>569
天保の飢饉どころか江戸の初期から他藩に走る百姓なんて問題視されてたが?
飢饉時の人返し令なんて中学で習ってるだろうに、家ある奴に家帰れって言ったとでも思ってんのかな? >>571
知らねえよ手持ち辞書にそう載ってんだから >>572
昔はハゲ山だよねそこ?
まともな木が生えてるのなんて福岡県の中部にあったが立入り厳禁もいいとこ >>553
古くは瀬振りと言われ、要は川沿いに定住せずに暮らしていた人達はいた ここまで柳田国男『山の人生』なし
嫌儲の教養どうなってんの
>>573
それはあくまで農業従事の百姓だろ
そうでない無戸籍、定住でない人間は江戸時代でも一定数いたという話だよ 病める人々だったか昔の精神病院の話読むと戦前は精神薄弱者とか浮浪者同然の人を見かけたらちょっとした仕事頼んでお礼に食事やお金を渡すなんて事が行われてた
近年まで災害起きると住所不定な人たちの稼ぎ時だったのに
廃炉作業は中抜き災害は持ち出しボランティアが前提になってしまった
マル暴並に警察や警察権を持った層の山徘徊してるホームレスの隠語よ、的が浜で注目浴びただけで明治期の幽霊や化物話より事例皆無ってもうわかるだろうに
宇宙人の存在の方が圧倒的に存在の可能性見いだせるレベルよ 笑
>>572
「サンカとされた」一部の人達は職能を持ったミナオシ(蓑直し)だったんだよな
この人達は、それこそ普段は定住農業で、農閑期や冬に日銭を稼ぎに流浪した >>580
聖、歩き巫女、猿楽、からエベッサマ、サエモン、チョンガレブシ、マンザイ、ノゾキなど遊芸民に至るまでその辺は本当多種多様だった >>343
お前しばらくネットから離れろよ
病気だぞ グンマーのグエン族みたいなのが50年か100年したらサンカと呼ばれるようになるんじゃないの
>>579
そして、それが定住ではない=悪として徐々に(そして完璧に)「社会」から葬り去られた一連の流れが、この「サンカ物語」の一側面
歴史的には縄文と弥生の話を思い出す人もいるかもだけど、人間の歴史はそんな風に微妙に要素を変えながら「繰り返している」というエピソードの一つなんだな さんかれあってアニメ思い出した
割とよかった気がするけど全く内容思い出せん
ただの山中漂白民だろ
たたら場なんて付近の木を切ったら拠点を移動させる
マタギみたいのは全国を周った
江戸時代に紀伊山中で何喋ってるのかよく分からん猟師が発見されたがその猟師は東北のマタギだったという話がある
>>556
各地にいたってことなの?
規模的にも地域に偏りがあったりするもんじゃないのかね >>108
自由自在ではないけど、里者と違う生き方で山の道を使っている人達はいろいろいたんだよ >>589
スレタイが嘘なのは事実だけど、漂白民はゴミだという君の認識もまたどこから来たんだろうか >>590
面白い話だな
そういう身勝手に動き回ってた人って罪に問われたのかな? >>590
マタギというか狩猟者は特に全国なんか回らん
彼らこそ、土地と山を良く知る必要があるから
サンカと言われる非定住民は、逆に言えば山と人里の狭間に生き続けてきた人々の総体 琉球人のルーツは中世グスク時代に西九州南九州から移り住んだ人達なんだってな
>>70
野生動物が住んでても文句言わないのと同じ >>108
大坂ー奈良の間でも公然と関所をパスするルートがあったよ サンカって語源とか意味知らんけど多種多様で
この1ワードで一括りにできない感じなんだな
戦中に身元調査を徹底的にやったけど実際は
ドヤ街の人間の戸籍把握できてなかったからね
江戸幕府の強固な関所越えもまず無理だった
だろうけどそれ以前は散在して移動してたかも
というロマンはあるよな
こうゆうスレがたつからケンモやめれん。
ダッピダッピダッピのクソのなかから
>>594
ハンセン病患者が四国で年中放浪していたけどお咎めなしだったのと同じ
そもそもハンセン病の人間だけが通る山道というのがあったしね >>595
あ、正確に言うと「定住民であったかどうかも分からない」だな
我々定住者の歴史から見て、非定住と見えたモノの総体か >>602
それっていわゆる虚無僧的な聖職者扱いだったんじゃないの?
狩猟を生業としてる人とは法律の上でも明確にちがうくない? そもそも「マタギ」が笑える
差別用語でも何でもなく穢多に鉄砲50丁貸したり百姓にも鉄砲何十丁も全国津々浦々どこの藩でも貸してるのに何撃ってたと思ってんだろ
中には押し入り発生で村で100丁借りた証文とか残っちゃいるがね
マタギ猟師と百姓(浦百姓)なんて東北のよほどの僻地でもなけりゃほぼ兼業なわけで、なんつーか、想像力も知能もないよな 笑
猟して「殺生」してるのに賤民ともエタ非人扱いもされないのは兼業がほぼほぼだからこそなわけで
漁師なんて武士の演劇で確実に「賤民」扱いされてるオチつきという
鷹狩やってる武士も自ら修羅道に落ちる糞野郎自認してるけども
>>599
そんなことはない
>江戸幕府の強固な関所越えもまず無理だった
実際の関所跡見て見なよ一度 >>577
柳田も含めて未解明なものに対する「トンチンカン」な推測する学者だらけじゃあないの
南方だのも含めていいこと言っててもトンチンカンな論のせいで糞味噌に無視されてるのはそういうとこ >>606
そもそも藩の境目なんて石置いてるだけってのも知らない馬鹿しかいないんだって…w
https://i.imgur.com/ibD6VKU.jpg
時代劇に出てくるような関所なんてほぼない、江戸入り用というオチね 脱藩が難しかったのって武士階級の人なのか?
それとも武士階級でもうろうろで来てたの?
>>57
Netflixにあるのかよ
全然観れないから小栗康平BOX買ったわ >>443
南紀出身の同年代だが
婆ちゃんが昔(大正?)の話で山賊おったとか言ってたな……
今でも熊野の奥地とかにいそう >>610
百姓なんて古代から逃散のが当たり前だし江戸期は走りと呼ばれてる
他藩で家と祝い金?付きで迎えられるのが多い
https://i.imgur.com/FoPSrdp.jpg
なんだかんだで各村の人別に「浪人、牢人」なんて平気でいるし全くいうほどじゃない、漫画の見過ぎ
ただ逃げたら藩のメンツかけて追っかけてくるし、他藩が匿えばほぼ99割家老が出ての話になる(いくら足軽であろうとも)
ま、「走った百姓」のトラブルでも家老出てくることも多いがね 炭焼きはあちこち転々と移動しながら山を借りて炭焼きする人達も居たからそういうのが回り回ってってなトコじゃないかな
>>609
国栖、隼人、熊襲、土蜘蛛、多禰、蝦夷
未だにこれがIME変換で出てくるのは「マシ」なのかもな
東遊、隼人舞、筑紫舞、国栖奏、大和奏 >>614
お前の文章汚くて嫌いだけどそれなりに本は読んでるんだな
もっと普通の文章にしたほうがいいよもったいない >>616
お爺さんは「しば」を狩るしかなかったレベルなのに薪どころか炭焼ける場所も限定的やがな
だからこそ昔からの名産地が残ってるわけで
当時の庶民が買えなかった炭なんて今でもお前らに買えるシロモノじゃあないけどな 笑 >>606
なんか調べたらガバガバだったみたいね
すげえ難しいって何かで読んだか見た気がしてたんだが >>619
オカルトは俺は好きなんだけど、それこそ歴史知識と良識がこのスレだと邪魔するわw >>620
無限に繰り返してるこういうトンチキなスレにはそういう言葉がお似合いだろ?笑
ごく稀に立つ良心の塊である浮世絵スレとかじゃあこうはならないんだよ
本なんか読むまでもなく当時の腐るほどある証文類少しでも齧ればいかに「そういうものに触れてもない物書きの嘘八百」ってのが手に取るようにわかるんだよ >>625
それは違う
元よりそういう形態の生活様式の人がこの島国で1000年単位で続いてきてたというだけの話 >>576
その程度ならミステリアスに語られる謎の山岳放浪民族山窩というものとは何か違うし普通に里人とバッティングするんじゃない 兆散という言葉はそういえばいつ出来たんだろう?
なぜそれが「悪」という定義で使われるようになったんだろう?
>>625
実際逃散したら困るの武士だし現政府みたいな重税なんかとてもじゃないがかけられない
重税よりもなんとなくレベルで他藩の知り合いのとこに逃げてる百姓なんて多いんだわ
それに家やって一俵あげたりして居着かせようと必死になってる藩なんか当たり前でね
飢饉で東北の百姓が一斉に逃げた時、幕府は最初は暖かく迎えたのが笑えるだろ
そのせいでとんでもない数が押し寄せて手に負えなくなるわけだが、お咎めなんかあるはずもなく
「関所」なんて古来から鈴鹿だのごく一部だろうに >>628
当然していた
そしてミステリアスでも問題視もされなかった
日本でも大体はね
でもいつからか、問題視されるようになったんだ
「異化」ともいう >>629
律と令の頃から悪だろ定期
平安「京ノ都」含めて律と令なんて永続的に続いてるフシがあるわけで >>630
さっそく↓の人が釣れてるけどw
俺はそもそも「兆散」という用語自体どうかな、と思ってる 多分というかほぼ絶対だけど実在したサンカも狭い範囲でいくつかの拠点を回っていただけで日本全国を回っていたなんてことはないよな
釣る釣らないの話じゃあないよなぁ…w
こういうのは定期的にアウトプットしとかなきゃ忘れちまうからなぁ 笑
この糞狭くて息が詰まるような日本にも
自由な生き方をしていたノマドが居たという幻想に酔いたい気持ちは分かる
そういうの現実には存在しないから
>>633
君は、平安当時の法律的な物も善と捉えているの? >>635
サンカなんて実在してない定期
もし山で人別外れてホームレスしてたら全自動で「非人」だろ定期 >>635
うん
でも、定住民にとっては「化外の民」、もっと言うと「蛮族」や更に言うと「人間ではない」と見える >>639
「非人」という定義って、どういうとこで使われたんだろ
エタヒニン、と言うのは被差別階級だと君はなんとなく思っているんだろうけど 大正生まれのばあちゃんは子供の頃天狗が子供さらうことは度々あったと言ってた
箕作とかは吉野で近年まで存在していたらしいけど
漂白民ではなくて山間の小集落の住民
>>637
破産した挙句年の差糞ゲイカップルが東海道旅行できてた時代は息なんて特に詰まっちゃあいないだろ
むしろそれを日本中が暖かい目で読んでたなんてジェンダーフリーの魁もいいとこ
犬でさえ旅行できなくなった現代よりよほど自由闊達、重いミツギが嫌なら逃げりゃいいわけで
たまに正義感で真正面からやりあってるのも自由でいいじゃないの >>637
笑えない位歴史の繰り返しだろうと思うのはまさにこの辺で
柳田國男がサンカを「見出し」、日本国民がそこに乗った時代もあったんだよな 現在でも戸籍無しの貧困層が1万人以上いるんだっけ
現代のサンカだな
明治以降も戸籍を持たない人たちが居た
それに変な物語りが脚色された
それだけのこと
玉石混交だったしほぼ石だったが98から06位までの田舎伝奇エロゲ楽しかったなあ
いい時代だったなあ
>>647
戸籍無し、はどんどん増えるよ
俺たち、戸籍が完全に機能している時代の生まれからしたら信じられないだろうけど >>639
君の言うホームレス説は部分的に正しくて一時的に元々いたコミュニティや生業から離れざるを得なくなった人達が存在していて
それを何世代にも渡って継続した「民族」みたいに言うのはウソなんだろう あ、いや今でも全然完全でもない。失礼
サンカの歴史というのは調べていくと戸籍(定住)と、そうでない人達との対比にも突き当たる
そこで、結構現実(現在)や未来ともどうなるか考える訳だけど・・・
>>15
これに宮本輝の『泥の河』についての言及あるがどんな話だっけ?
『蛍河』とごっちゃになっている
蛍で女の子と服が透けるのか『蛍河』で、年嵩の父親が部下に裏切られるのが『泥の河』だっけ? >>652
違うよw
>一時的に元々いたコミュニティや生業から離れざるを得なくなった人達が存在していて
日本人はこの1000年位でも農耕が基本でだいたい定住民だと思っている? >>650
グンマーのグエンも戸籍無いだろうからな >>656
少なくとも荘園制や藩制が整った中性近世以降はそうだろう
もちろん百パーセントじゃないだろうけど 50年どころじゃないだろ
俺がガキの頃の話だから70年くらい前の話だぞ
明治維新まで山伏は20万人近く居た
何をして生計を立てていたかを考えると
明治新政府に弾圧される理由も分かる
高畑のかぐや姫の物語に出てきた捨丸とかいう男は
サンカがモデルになっているらしいな
京都の灰屋川にあった小集落は明治になって発見されたんだっけ
京都ですらそれなんだから戸籍不明の山人は相当居たはず
>>641
足りてないなぁ脳みそが
まさに燕雀安知鴻鵠之志哉、だな
https://i.imgur.com/zzH5k9G.jpg
バンタなんて非人手下そのものだがオンボは?とね
これにエッタ非人が載ってないのは「賤民の称」がなくなったからで「職業自体の賤」なんて庶民にとっちゃあまだまだそのまんまなわけでね
歌舞伎役者なんて支配から抜けたから助六で喜びを表したわけで、な?わかるだろもう?
穢多の斃牛馬なんて「株」として売買されるほど高額だからこそ岡山なんかじゃ百姓ができない「華美な格好」してるような高給特権で、事実、弾左衛門なんて幕末には歴とした1万石の「大名」とした
この番付のどの職業が江戸期に「穢多非人の支配下だったか」なんてトンキン大の名誉教授でもわからんけどな、各藩の定義で変わるし
明治の貧困スラムを「特殊部落」として穢多非人のそれと味噌糞にしたせいで定義もイカれてるが
ま、「斃牛馬株」をまとめて10両で売り買いしてましたくらいまともな義務教育だったらサンカみたいなの信じるバカもいなかったろう
話がギュンギュンそれてくな、すマソ 山中にある真言宗の寺をたどると瀬戸内からでも日本海からでも京都まで行ける
所謂サンカはファンタジー
タックスフリーで物流を担ってた人は中世から存在した
このスレを見てると藩を跨いで移住した農民を不定住民みたいな見方をしてるやつがいるな
そいつらが季節ごとに移るなら不定住民だろうけど現実的にはそうではないだろ
>>623
旅芸人なんか芸を見せればスルーだったらしいしねw >>660
なんで嫌儲に80歳近いジジイがいるんだよ そもそも江戸時代に無戸籍なんてメリットがない
子供生まれたら大体1両以上or米何俵かは貰えるのに山中にいる意味がない、現代のニート的な発想はやめろよな 笑
労働力が枯渇してる上でテグスやらの発明があって、イワシ肥料にする余裕がある上で百姓はウンコまで買い取りしてくれるのに山にいる意味はないよなぁ
熊野なんて猪垣作るくらい獣がいる山は当然「危険」なわけで
な?宇宙人のほうが居そうだろ?笑
>>671
へー
>子供生まれたら大体1両以上or米何俵かは貰えるのに山中にいる意味がない、現代のニート的な発想はやめろよな 笑 >>661
>何をして生計を立てていたかを考えると
明治新政府に弾圧される理由も分かる
なんで?反政府的だったから? >>674
?
天保あたりじゃ7歳くらいまで米支給とかもあってるんだよなぁ 今はサンカいないのかな?
ここまで不況、社会が不安定になるとサンカみたいな
生活をしているひとがでてきそうなきがするが。
>>676
その米支給は、誰を対象にやられたの?
当時だから、戸籍とされた宗門帳に記載された人に対してだよね >>677
いない
というか>>1の定義のは昔からいないし、日本の歴史上存在もしない
謎の民族とかいうなら尚更 >>677
もう車中泊ホームレスをサンカでいいんじゃね?
実際に存在してたサンカより圧倒的に数多いだろうし 笑 >>680
シンゾウやヘイゾウは実は忍びの家系だからな
痕跡は残さんさ >>682
最初から見たけど、やはり君のような人がサンカをでっちあげる人だよな 封建時代はまさしく人は力だからな~ 自由人がいられる社会じゃない
佐渡くらいかな
>>679
江戸時代でも、後にサンカとされた人達はいたし生きてもいたんだよ
君がまさに知らない領域で >>685
それもちょっと違う
サンカと言われた人達は別に自由を志向した人訳でもないし、また、封建時代には人の自由はなかったというトレードオフでもないと思う >>685
佐渡?笑
江戸期の極悪犯罪者が最も嫌うとこだなぁ
佐渡がフリーダムな地とでも?それこそ日本トップレベルで厳しい目光らせてる地域だよ定期
左翼諸氏の言う奴隷的契約であった江戸期の「奉公人」なんて仕事バックレて伊勢参り行って戻ってきたらよくやったぞだよ
左翼諸氏の言う奴隷的契約下にある「奉公人」が伊勢参りしたいって言うと、主人が金渡して無事に行って来いって言うパターンもあるなぁ
現代より自由じゃないのかね?馬鹿なの? そういや昔の日本は禿山ばかりだったな
薪も高価だったし
>>690
薪が高いのに炭焼きが多いはずもないってのは物価見るだけでもわかるわな
そもそも「炭焼き」が確実に賤業視されるのは明治後と思うよ、炭焼きについてはそんな詳しくないけどな
この辺の推移も糞味噌に定義したから戦後の馬鹿の白痴に拍車かけてるんだよなぁ 佐久の山中出身の母親が
箕を売りに来る人たちがいた
福島の方から来る
普通の人間と違うって大人たちが言ってた
なんてことがあったぞ
>>692
どうせ昭和の話だろ定期&普通の人間と思われてない職業なんてこんなにいるわけで
それかメクラかなんかじゃないの母親?
https://i.imgur.com/zzH5k9G.jpg >>690
延宝5年の入会山の取り決め
https://i.imgur.com/c5dAInT.jpg
入会山と言うのようのは、どこの村落でどこまで山に立ち入り木を切り薪木を取って良いか ぶっちゃけひとりやふたりが山に逃げ込んで死ぬまで隠れて生活する、とかならともかく
何らかの集団が下界に一切存在知られることなく
なんの痕跡も残さず数世代重ねるとか不可能だろ
>>663
今でも脱落地って誰の土地でもない、国の土地にもなってないとこなんてわんさかあるわ
大概畦とかなんだけど >>446
敬老木綿ってガチでいるんだな
むかし対馬丸の生き残りと称する木綿もいたケド、案外ほんとうだったのかも・・・ >>695
下界というか、人間の強い集団側が「敵」を駆逐し忘れ去ることは可能だな
人間の生理的に >>700
人間が生物としてこの星の王となった力の源泉は恐怖と、その忍者とかに対する想像力なんだな・・・ >>699
ぶっちゃけサンカとやらが空飛べる特殊能力でもない限り
移動経路なんて下界の人間とほぼ変わらないはずなのに
なぜか痕跡すら残らないという サンカなんて馬鹿でもわかる嘘八百を盲信して聖徳太子の富士登山信じない白痴が怖いよね 笑
どうせ犯罪やったり村八分されたやつ、徴兵逃れみたいな表の世界じゃ生きていけない今で言うケンモメンみたいなのが山に逃げ込んで共同生活してたんやろ
>>704
定住していない人間は罪、という意識はいつから君に刻まれたのか
実は君の親の世代はそうでもないかもしれないのに >>698
関東大震災経験したモメンもおったなそういやw 高知ツーリング行ったとき雨宿りで寄った図書館
郷土資料読んでたらそんな記述あった
落人集落の延長で山賊集落みたいなのが昭和の戦前まであった
夏は旅人を襲い冬は海辺まで降りて乞食をする人びと
いまも四国山脈に面影のある集落があるらしい
税の概念からに決まってるだろうに白痴だなぁ
有史上、全世界的に見ても税を取れないからこそ非定住者は迫害or賤視の対象が根源であってね
江戸期にそんなんいたらチクって小銭貰う輩なんて山ほどいたろうし、チクられてもダメージないどころか住処まで用意してくれるのに現実的にありえない
江戸期のエッタ非人さえ与太話にしないレベル
山中の交易路はあったし、交易を担う人々は居た
交易なんだから良民と関わらないなんてことは無い
三角が“サンカ”を創作するにあたって元ネタにした存在はあったの
それとも大部分が想像力を働かして拵えたことなのか
まあそれこそ、三角が全部捏造した訳でもないわな
そして、日本人が今も昔も信じたい、信じたかったこと
サンカの歴史というか、サンカという幻像の歴史は本来は今の日本人にこそささると思うけどね
サンカ関係無いけど
20年前、新宿から総武線乗ったらネギ背負ったお婆ちゃんをたまに見たけど
あれなんだったの?どこかに売りに行くんだろうけど、何処に?
>>79
たまにこういう教養ある奴いるから嫌儲をやめられないんだよ 羅宇屋、鋳掛屋、箕作、野鍛冶
村人からすれば稀人だけど普通の行商人
サンカという幻の「敵」を作り上げたい(と言うのがいやなら「作り上げてしまった」)「日本人の歴史」の一節でもあるんだな
>>713
総武線の背負子のばあさんとかはたまに聞くな
2000年代でもいたのかな いろいろ読んだ感想は、四国にはお遍路さん狙いの強盗が居て、それは周辺の集落のならず者の仕業だけど、なあなあで済ませたいから山賊や山の民を捏造して責任押し付けた、って感じっぽい
>>712
とりあえず物証がないから
サンカとやらの定義すらまともに決められないわけで 「風の王国」とか
デラシネとか言ってた人が作り上げたファンタジー
ノマドへの憧れでしかない
>>696
なんでこのクソコテは自分にレスしてるの >>710
もう少し突っ込めば当時出来たてホヤホヤの部落同盟コト水平社がツッコんできたから警察が適当に言い訳したのがサンカの正体と思われ
それ鵜呑みにした馬鹿があたかも大多数実在してたように書いたから後世の白痴が「いるはずもない幻」追っかけてるだけというね
サンカ部落って定住しとるがなをツッコむべきだし、的が浜以外でロクに聞きもしないという
いずれにせよ、エッタ非人や貧困スラムを「特殊部落」と定義して取り込んだ水平社だのがそういう貧困層を見逃すはずもなく、実在したならこれに「サンカ」だの嬉々として書いてるわけで
https://i.imgur.com/QTbNpoU.jpg まぁうちの祖父の子供の頃はたしかに山の道とかに行商人がいてたらしいよ
峠の交流が活発だったしね
村を置いて離散する農民とかもいたらしいし、流れ者もいたろう
江戸後期や明治くらいの文書には
記録されてるらしいじゃん
内容はともかくそれなりにおったんやろ
三角の小説とは違うやろうけど
>>728
まともな記録がないから三角の捏造が唯一レベルの根拠になって
それが崩壊したら「サンカという何らかの独立した集団」の存在自体の根拠すらないわけで >>721
山のホームレスというより普通に家持ってる人達が保存食作るのに失敗
冬に食えなくて海辺に降りてきて海藻拾ったり乞食やったり単純労働に従事する
そういう謎の集団が伝説になったんだと思う >>724
TVKでたまにやってるなw山下清
でもあれも含めて、今の人間には分からないとなっているのかというのは興味深い いつの時代でも、それこそ現代の日本でもアメリカでも住所を持たない、持てない人間は一定数いるでしょ
それでも食って生きてんだからな
>>721
定住が前提な君だとそういう視点になるのかもな >>711
アホ警察のネーミングセンスが良すぎたせい >>729
貧しい人がおったというだけやろね
ボートピープルみたいなのも一定数いたし
山にもいたやろなと思う サンカとやらの設定なら普通
山の中で「未知の原住民、山窩を見た!」とかになるはずなのに
警察やらで出てきて弾圧される云々のサンカは
なぜか街中で定住してるんだよな
https://i.imgur.com/4Tl6uSm.jpg
なんか的が浜ググってたら部落解放同盟大分県連合会さんのページ見つけたけど、昭和10年には該当地域は特殊部落になってないみたいで草なんだけどね
https://i.imgur.com/YDK1o8u.jpg
まぁ、いろいろと面白いなぁ 事実としては水平社が警察に部落差別の抗議したが、警察曰く「サンカ部落」で退去させて廃屋焼き払ったってのを水平社は認めてたはずだけども
いろいろと狂ってるよな
ここの真っ赤な奴並みに 笑
火事怖いし炭焼きなんかまともにさせてもらえなかっただろうし、そもそも日本で大規模な山火事なんて起きたこともないからいろいろとわかるよね
ああ、神奈川だかのキャンプ場で子供が消えたのはまだ子の人々がいて連れ去られたのかもな、でも北朝鮮の可能性のが高いのか
>>737
うん
なんでか、なんでそれが悪と定義されたのかという話でもある サンカの存在が怪しいなら俺が読んで心躍らせた宮本常一は嘘だったってことなのかよ
>>719
調べたら2012くらいまではいたらしい >>743
?歴史で弾圧されたサンカもどきは普通に定住しているわけで
その「悪」の定義がわけわからないわけだが
山狩りしてサンカ皆殺しにした、というならまだわかるが >>621
限定的も何も山仕事の大半は炭焼きだろ
家族で焼畑込みで3年スパンで移動する形が多いけどそうじゃない形態もあったんでないの ここまで「ウメガイ」って単語が2回くらいしか出てないのがなんとも。
あれ今だと所持できないんだよな・・・。
>>70
昔見たイギリスの北部辺り歩く番組で道沿いの果樹やキノコは誰でも収穫してよいってなってるの思い出した
別の本でも中世には共有の森や小麦畑があって貧乏人はそこから薪や小麦収穫しても良いとかさ
キリスト教の施しや共助の概念かな >>748
定住ではない=悪となったんだよ
明治の壬申戸籍から決定的に
これ知らない人結構いるのか >>752
江戸時代は街路樹に実が成ってたらそれを食べてもいいみたいな話を5ちゃんで見たことある >>753
だから歴史で弾圧された「サンカ」は
「定住」してるんだが 柳田國男の山の人生から三角寛
その後に網野善彦あたりから隆慶一郎あたりに繫がる流れがあるよな
柳田の後に三角寛が出てきたのがファンタジー化の原因なんだろうけどそれを許して支持した世の中の雰囲気とかも分析しないといけないんだろうな
>>754
朝廷が街道に柿の木植えて腹減らした旅人が食えるようにしたってのは聞いたことある >>756
サンカが使ってるとされた短刀というか脇差の名前
>ウメガイ/ウメアイ
クサビみたいな三角形の両刃の鍔のない刃物で、サンカはこれをサンカの証として持っている、とされてた。
・・・でもサンカのことを有名にした件の本にそう書かれているだけで、実物が見つかったことがなく、「これが本物だ」とされたのはみんな現代作のニセモノだった。
結局創作だったらしい。
でも妙に有名なのでレプリカが結構作られてた。
今は例のダガーナイフ規制にひっかかるので個人で所有してると違法。 >>517
面白い話が全くない、ただメタ情報と推測を延々と繰り返しているだけ
夜眠る準備に最適な内容の無いスレ >>759
フィクションとしては面白いが現実味は微妙だな
刃物を作るには鍛造の技術が必要で定住も必要だろうからな >>755
?
してない
1970年代でも全然してない >>757
あるかなあ
>柳田國男の山の人生から三角寛
その後に網野善彦あたりから隆慶一郎あたりに繫がる流れがあるよな
いや知らんけどw >>762
それならまず「定住せざるは悪」と
サンカを山狩りして捕らえた記録なりがでなければおかしいわけだが
そこをすっ飛ばしてなぜか的が浜のサンカもどきは普通に定住してるんだよなあ >>758
元ネタってのも変だがそういうのはローマの街道辺りからか 東日流外三郡誌といい山窩小説といい偽書には妙な魅力があるよな
>>761
そうそう。
よく考えると「これがサンカである」とされるものと矛盾してるんだよね
>ウメガイの存在
本当に昔から使われてたのなら何らかの形で遺物として見つかってなければおかしいわけだし。
なおレプリカナイフとして作られたものを実用してみた人によると「本当にこの形だったとしたなら使いづらくて実用性がまったくない」ものだったとか。 30年ぐらい前に近くの河川敷に謎のプレハブ集落はあったな、子供の頃朝鮮人が住んでるって聞いたけど
同和とかって話も聞いたが真実はわからん
>>763
俺の考えだけいうと
一種の山岳信仰から始まったと思うんだよな
江戸時代に平田篤胤が天狗に攫われた寅吉とかいう小僧のインタビュー書き留めてたけど山に何かいるって思想はずっとあったと思うんだよ
一方で明治から国民国家になっていく中で山にいる何かにも納税する義務が生じたと
ある種納税しないということから国家や権力に所属しない=自由というファンタジーが生まれたんじゃないかと
沖浦和光の本では確かにサンカは民族ではなくおそらく天保あたりの飢饉で逃散した広島の農民が中国山地に逃げ出したのがいわゆるサンカであってそれ以外に漂泊民はいたであろうと書いてるし
証拠として紀の川での漂泊民の写真とかあったと思うけど沖浦先生が言うには1950年代にはこうした人々は消えてしまったというけど個人的には内水面漁法の改正がその時期にあったから関係あるんじゃないかと思ってる
漂泊が国家の体制に取り込まれるストーリーとして如何に捉えるかという部分で盛りに盛ったのが三角寛という立場だなあ 三角寛か
賢モメン達は宮本常一の忘れられた日本人とか好きそうよな
>>767
これに関してはサンカと関係あるかわからんけど存在したぞ
数十年前に秋田に住んでた俺のおじさんが山で拾ってきた
くないをでかくしたようなやつ
ガキの頃それで遊んでたけど、かなり古くて使い込まれてた
鉈と同じような素材と作りだったけど、剣先状で鉈としては使いにくかったな
おじさんの家に行けばまだあるかもしれん >>773
山岳信仰ってこの国の信仰だとどこで始まったんだろう? 定住農耕民以外の諸々(水軍・水運関係、山伏、マタギ、炭焼き等)に落人伝説やら稀人信仰やら面倒を押し付けるための畏怖やらがごちゃ混ぜになった民間伝承が各地にあって
それを元に大幅に脚色して創作されたオカルトファンタジーな総体が三角の山窩って印象
>>778
山岳信仰は縄文以前からあったと思うよ
世界中の原始宗教で普遍的にあるし
山伏的な山岳信仰も元々あった山岳信仰と仏教の融合だし、どこが起源とかはわからないんじゃないかな >>780
そうかなあ。まあ一般論的ではあるけど
>山岳信仰は縄文以前からあったと思うよ
世界中の原始宗教で普遍的にあるし >>766
結構笑えない「日本人を惹きつける魅力」かもなあ
負の >>781
例えば有名なものだと木花開耶姫命は富士山の擬神化だし、少なくとも平安時代には山は神の家、もしくは神そのものだと認識されてるね
人は死ぬと山に還って祖先と暮らすという考えも広くあるから、大和神話成立以前にはもう山岳信仰的なものは普遍的に存在したと思うよ >>207
慰安婦とか昔の政治家が俺が兵隊におった時は~って普通に自慢話でしゃべっとるやん >>780
自然信仰は恵みをもたらすものと理不尽に害をもたらすものへの畏怖だもんね
太陽・月、海、川、山
日本は火山地帯だし山岳信仰強かろう お前ら炭焼きの事忘れ過ぎだよね
燃料全部炭なんだからそりゃ必需品で金にもなったんだよ
>>787
だね
今は神様は願いを叶えてくれる的な存在だけど、ちょっと前までは関わると祟られるし、暴れないでくれとお願いするのが祭りだったしね
理不尽な自然災害に対する畏れが神格化したものだから、起源をたどるのは相当難しいと思うよ >>766
嘘が大好きな日本人は偽書も大好きってことだろ >>15
>>446
なにそれちゃっかり生き字引いんのかよモメン >>785
大和神話以前にだとは思わんな
広くある?いつから?
>人は死ぬと山に還って祖先と暮らすという考えも広くある これとかも実際にはいつから?
>木花開耶姫命は富士山の擬神化
古事記の時から本質的にあったものでもないよな
その当時は富士山なんて神格化もされてないし
いつからと起源を明言できないって話にいつからって
根拠のないものに根拠をこじつけるのは創作または捏造だよ…
鉱物探しの山師的な事もしてたんだろう
百済王氏が奈良の大仏の金を東北で見つけたのは偶然じゃないと思う
>>738
2枚目、部落地名総鑑の原典かな?
初めて見たわ >>1
ビジネスだろ
なんで男はみんな丸坊主なんだよ >>57
泥の河ってネトフリで見れるのか
カニに火を付けるシーンしか覚えてないけど 
>>1
この記事クッソ胸糞悪すぎて途中までしか読めなかった
こんな人の道に外れたことして生きるのが辛くならないんか? >>185
真実だけを書き残した文書なんてないのさ >>794
富士山の祭神が木花咲耶姫となったのは江戸時代
それ以前はかぐや姫で、かぐや姫の物語は富士山の縁起
それ以前は弁財天で、富士の樹海の下には弁財天の霊場?があると言われていたらしい
上記は平安以降かな?それ以前は解らないが、何らかの信仰はあったはずだよ >>207
慰安婦で何を嘘ついたの? 政府すら認めてんのに スレの頭の方で水上生活者って見て横浜には普通にいたよなあって思いながら読み進めてたらやっぱそうだったんだな
逆に横浜以外だと結構珍しい存在だったのか
>>804
江戸時代に部落認定済→昭和10年に部落認定済→現在部落認定済
江戸時代はただの野原→昭和10年に部落認定されてない→現在部落認定済
的が浜はサンカ部落→昭和10年に部落認定されてない→現在部落認定済?
この辺の推移を知れる貴重なものって認識でしかないけどね
昭和10年のこれは1世帯1人レベルまでご丁寧に記載してくれてるのは割と重大と思うよ
>>808
事実の記述に嘘八百が交じる貴重な書き起こしだなぁ
例え先祖が武士であれ穢多であれサンカ(爆笑)であれ出自について言及してんのがただてさえおかしいしんだがね~
関東の山を行き来するサンカってもう 笑 石川の方に山の中で暮らす人々がいたって聞いたな
北海道開拓の時に多くが移住したからいなくなったそうだ
嘘つけ間抜け
いちいち伊達市や東広島だの出身地で居住地分かれてるレベルで集団として移動してんのに白痴馬鹿だよなぁ
>>15
ジジモメン一歩手前だけど
そんな連中知らないわ
どこの地方にもいたのかな ( ゚Д゚)「昔はたくさんいましたね。縄やわらじや嵩を売りに来てましたね」
(´・ω・)「昔の農家さんが使ってたようなものです」
(´・ω・)「ナウシカでいうと森の人か虫使いですかね」、
>>343
最低すぎるわ
デマとアイヌをしれっと並べて
Dappiの支持か? >>822
縄や草鞋や笠なんて佰姓の重要な副収入定期
売れるしミツギの対象外なら誰でも作るわ 八つ目の乳に意味感じないけどなぜか知られてるのが面白い山伏
>>767
ウメガイというか日常仕事で使う小刀について言えば個々で使いやすい形状があっただろうし両刃を好んで使う人も中には居たくらいの事を
サンカが共通的にあの形を好んで使ってたみたいに誇大に書いてるんだろうな
最近でもホームセンターとかで売ってる山菜取りの小刀はウメガイみたいな形状だし昔からあの形が良い人もいるんだろう 50年後ぐらいにはケンモメンも都市伝説になってるよ
山も水上も難易度高そう
俺は日本版トンネルピープルになりたいこれぞ新世代の謎民だよ
>>1
ふーんと思って読んでたら
役所が生活保護ぶん取ってて無茶苦茶や 北関東とか中国地方とかの山だな。寒い方にはいない。三角はともかくまともな研究もある。
読み切り漫画でスレタイみたいな民族を題材にしてたのを昔読んだことあるんだけど
出てこないな
今も多数の言語多数の民族が共存する中国
少数民族は徹底的に迫害して同一化、日本語すら都合のいいように作り替えて伝統を捨てた日本
>>142
昔はまず炭焼きや林業の需要が桁違い
今では登山者もあまりいないような道が自動車も鉄道もない時代は割と交通量があってちょっとした宿場だったとかザラ >>836
ないわアホ
ほぼ大正期に降って湧いたように出てきてるし、それらのソースがこれまたほぼ「警察の話」
好奇心旺盛すぎるリテレートだらけの時代で圧倒的に記述は少ないしほぼほぼ「サンカという名のただの浮浪」で結論づいてるのが散見できる程度
既に居住地どころか定住→出稼ぎレベルの徘徊も把握されてるのにどこが「幻の放浪集団」なのかと
https://i.imgur.com/VnzfOYS.jpg
新宿のホームレスや足壊死の奴にサンカの子孫だの言い出しそうな統失の妄言に等しい話しよ
な?白痴か知障しか信じないだろこんなの 笑 落ち延びた平家の子孫も笑えるわな
鎌倉府に平氏筋どれだけいたかも知らない学のないド田舎の白痴の妄想に過ぎない定期
平家方で罪に問われた奴なんて明確なのにとるに足らない奴の一族郎党まで皆殺しになるはずがないだろうに 笑
>>843
そんなの普通の農民でも居るだろ
定住しないで移動しながら暮らすんだよ。
まぁ住居らしきものも有るらしいが >>427
祖母が戦後のどさくさで土地奪われて旅芸人になったけど祖父と結婚して落ち着いたって言ってたな
戸籍すら危うい根っからの人って少ないのかも >>845
なんだそれ?
山下財宝だのは隠退蔵物資の事件があったわけであながちない話じゃあない
サンカ自体が紛いな上に定住せず世間と関わりを断って放浪してるなら「資金」なんていらんだろうな
ただの行商人である~女どころか蝙蝠の安だの妲己のお百だの実在性はおいといても個人の素性あさるの好きな時代の人間がそういうものを見過ごすはずがない
ただの素性の知れない浮浪なんてほっといたらそれだけで「御家」に咎めがある時代の発想に欠けてるんだよね~
ま、こんなの戦後の白痴くらいしか騙されないンだよ >>842
非定住型の人たちや山に住んでたまに人里に降りてくる人たちをサンカと呼ぶ方言みたいな言葉が一部にあって
それが警察用語や行政用語のような形で全国的に広まっていったんだろうな
そっから三角寛とかの研究とも創作とも言えないような幻想的な設定が加わっていって独自の文化や言語を持った民族みたいな扱いができた訳だけど
最近のサンカ本でも三角寛の創作を取り払ってもサンカという集団が居たという幻想まで捨てられず
取り上げられる人たちがサンカという自覚のないまま強引にサンカカテゴリにはめられてるケースが多いと思う
サンカのような生活を送る人はそれなりに居ただろうけど
起源もその程度も多種多様で一律にこういう集団って言いきることが出来ないというのが実態なんだろう 
>>817
列挙されてる出来事の具体的にどれが嘘なの? >>849
知らんけど優秀な奴を大学とかに行かせるのに
そういうのが有ったとか
何で読んだかは思い出せない。 宮崎市内だけどウチの母親70くらいは幼少期に派手な服着た一家が近くの無人神社の社に寝泊まりしてたって言ってたな鍋とか修理してくれるんだとひと月くらいいたら居なくなってまた同じような連中が数ヶ月後とか一年後とかに来るらしい
あれをサンカと呼ぶのか単なる浮浪者か分からんがジプシー感はあるよね
1人でも保護できてたらサンカ語の研究ができたのにな…
>>858
その「ウメガイを使うのがサンカ」という定義にすると
サンカなんて存在しない、ということになってしまう 江戸とかだと杣と禿げ山ばかりで
山に見かけない複数人が居たら集落の財産奪う山賊じゃんね
って言うマジな考えよりも
明治以降昭和末期まで存在した謎の移動生活者が居たのだから
その亜種だって考えには同意出来るわ
>>285
バカ発見
チームワークで獲物を疲労させて分業を徹底するのが狩猟やぞ 当時の警察の言う山窩と現代の白痴馬鹿や当時の白痴馬鹿の望むサンカの正体が大正期に既に乖離してるのがよくわかるよなぁ
警察の言うマル暴やマル走を古代から存在してた集団のように考えるaiueo並の統失みたいなトンチンカンな話がオチだわ
徳島で消えた松岡伸矢くんはこのサンカに連れ去られたとかいうトンデモ説を見た
山奥の道にボロ建ててきのこ売ってる人とかその末裔じゃないの
戦後の農地改革でうちも土地とられて本籍は違う人の土地
>>871
「その刀を使っていた集団」なるものは
三角のファンタジー小説以外に存在しないからなあ
むしろそのファンタジー小説を元に作られた刀というか 歴史のロマン これが大事や
冷静に考えてみ...昔の山々を
現代人の思う"田舎の山"はみんな人が住んで田畑になっとる
山々は燃料のために肥料のために荒らされて木は少ない
建築木材のために吉野や木曽の山奥に人が入って木材ラッシュや
漆器の材料を求めて職人さんがガチ山奥の広葉樹の良い木を探し回る
痩せた土地で肥料も買えないとこじゃ焼き畑しつつ山間を移動する
夢もロマンもないわな。 サンカ!山窩や!...これならロマンがある ロマンは大事や
>>869
単純に法律的に排除されるかされないかで
そういうサンカぽい生活を送りつづけるかどうかがまず分かれたというのと
昭和の半ばまではギリギリ社会制度とは無縁な生活環境も残ってたけど
どんな山奥でもガスや電気みたいな生活インフラや学校教育に貨幣経済が行き渡って
戸籍も住民票もあった方が便利という社会が実現されたから
サンカ本に出てくるような人たちも定住性を持って現代社会の枠組みに組み入れられていったんだろうな
それでもあぶれる人はホームレスになったり普通に生活してるように見えて実は無戸籍者みたいな形で発見されてたまに社会問題になったりするんだろう サンカ否定する奴いるけど、東南アジアには反政府的な(非政府的な)ゾミアって山の民がいたやん
山だらけの日本にもいてもおかしくないと思うが
>>876
で、そのサンカとやらは
ときの朝廷や幕府に反抗して戦った記録でもあるんですかね >>872
サンカ云々とは別に個人の好みで先の尖った幅広だったり両刃だったりする山刀というのを使う人が居てそれが今でも市販されてるけど
三角寛がそれをサンカの設定を創作する時に取り入れただけじゃないの
ウメガイという言葉がどこから来たかは知らん 空調の効いた部屋でスマホ片手に議論してるからそんなくだらない説が広まるんだよ
実際に山に行って一晩過ごしてみたらいいのに
ああこんなとこで暮らすの無理だわって一発でわかる
>>877
そもそも戦わないだろ
移動性が高いんだから
政府がきたら逃げるだけ
そもそも、高地の貧乏人に危険を冒して役人はこないだろうw >>882
何一つ存在した痕跡を残さず逃げる透明人間か何かかな? >>884
政府からすりゃ山の民を追うメリットがない
そもそも、役人が山登りする理由もないw >>885
記録も何一つ残さない
存在した痕跡すらない
空でも飛べる特殊能力持ちかなにかかな? ちなみにサンカ捏造で有名な三角寛は元朝日新聞の記者
もう全てが明らかじゃね?
奈良の南部なんてまだ修験道やってるやつ居そう
ゴルゴ13の持病治療してた回で出てきたやつら
山の民だとかサンカみたいにひと括りにして扱うからおかしくなるのであって
マタギなんかは宿場の用意された街道とは別に尾根伝いに移動する手段を知ってたりとか
公的な記録のあるもの以外にも点在的にそこの土地特有だったり一部の職種だけの移動手段は存在しただろうな
折口信夫が通ったっていう浜松の奥地の京丸集落見に行ったことあるけど
そこが江戸時代発見されるまで数百年存在を知られなかったっていうのはさすがにウソだと思ったけど
寺も僧侶もいないようなそういう山奥の集落なんかは戸籍替わりの寺請制度も行き届いてないだろうし
カネも使えず物々交換基本だろうし
同じ山奥でも街道沿いなんかの人里に住んでる人たちから見ても価値観や生き方含めて別世界の住人だろう
公的にはまともに税の徴収もできないようなその他の区分で片付けられる非定住者や山や川で生活するような人たちに
共通の文化を持った山人みたいな構想を持って柳田国男みたいな民俗学者が取り組んだけど
結局それは小集団の点在で山人構想は学問としては破綻したけど
そういう幻想をサンカという文化集団として再構成してしまったのが三角寛なんだと思う
サンカ幻想は武功夜話とか東日流外三郡誌と同質なんだろうが
今でも名の通る立派な学者でも騙されて信じちゃうこともあるし
それが流布したあとは完全にそういう話を消し去るのも難しいんだろうな
>>887
明治になってサンカを山狩りして捕らえた、とか
そういう記録も一切なく
大正になって別府の海辺の街中にいきなり出てくるのがサンカとやらな 鮫島事件みたいなもんか
アウトロー板発の工藤明生もいたな
>>881
これ
食いもんねえし季節性だし水飲みながらじゃないと移動できないし旅のように移動しながらなんて無理
住処の選定から作成考えても最低一年か数年毎がいいところ
人流なければ繁殖も交雑も起きないし2〜3代で終わる >>570
https://i.imgur.com/p9tUsWl.jpg
木こりってののイメージも「戦後の白痴バカ」の想像と明治以前のそれとじゃだいぶ違うんじゃあない? 薪も拾ったって湿気っていてすぐ燃えないから
すぐ燃える季節もあるけど燃えない場合もたくさんある
移動しながらってのは本当に困難
土曜日に賢くなるスレだな
こういうのは楽しいんだが人権に絡むから学校教育じゃ取り扱いづらいよな
>>602
でしか触れられてないけど
「当時のハンセン病患者」というのもいわゆる「漂白民」の重要な要素だったんだよな… 戦前まで峠道とか未舗装のクソ狭い灯りもない今で言えば旧道で
そりゃ山賊いたり女は強姦されるの当たり前だし
茶店と万屋が合わさったような掘っ立て小屋の店が1軒あってもそこは旦那は出稼ぎで妻は安い値段で体売ってるとかだし
よほど重要な街道で往来のある道でもなければこんなもんよ
それも戦前の昭和の初めでも

>>863
嘘八百と断言したんだから>>852に答えてくれない? >>901
松本清張の「砂の器」はまさにそういう話だったな・・・。 >>901
ハンセン病が漂泊の民?きっつ 笑
洛中洛外図や行幸図に癩者(であろう者)が平然と一般人と見物してたりするし、大谷吉継なんて好例がいるわけで疱瘡だのが流行ってる時代の人間はもろもろ逞しいもんよ
病気なんてもんより漂泊が許されるなんてありえないし、各種の病の蔑視賤視なんてコッホ時代の産物としか思えない隔離の仕方になるという
武士でも将軍でもエッタ非人でも疱瘡のアバタ面だらけなのに特別にハンセン病だけ取り上げてるのも近代ならではって感しかしない
ハンセン病だけが前世のカルマのせいとでも思ってんのかと
ハンセン病だけをクローズアップして特別差別されてきた感を叩きこまれた「戦後白痴史観」ほど滑稽なものはない 笑
伊弉諾の国産みを他国や宗教の伝承と比較したり、比喩をどう捉えるかを真摯に研究した方がよほど健全だろう 未舗装が悪も笑える
車通らなきゃむしろ足に良い、三和土然りで踏み固められたものは悪くはない
山賊の類いなんてのもなぁ
中国なんかじゃ有名な山賊はいるんだがね、そんなものが居たら即誅殺したがるだろうよ、昔の為政者は
そもそもいくら戦争しても強姦だのに結びつきようがない明治以前の時代への想像力が足らんのだよ白痴の馬鹿は
大衆の前で強姦して喜ぶ性癖すら以前の日本人には皆無の発想としか思えない
「清盛の妾」なんて悪例が存在してるが中国人でさえ嫌うレベルの趙高王莽と同一視されてるのが庶民にまで浸透してることも理解できてなけりゃ、馬鹿の「現代白痴史観」が横行しても当たり前ではあるがな
>>906
山賊と言うか近隣の村の若いのがちょっとあそこの峠行ってくるわというノリで
旅のもんカツアゲしたりとか女に乱暴するんだよ
でもそこ通らないとどこにも行けないというのもあるし
強姦されたところで今よりも被害意識が薄いし何より顔見知りだったりするレベルで
しかもそれが田舎だと昭和初期まで普通にあったぐらいの日常風景だったと
それを人が3人横に並んだら終わりの林道みたいな道でやってたの
俺が言いたいのはサンカみたいに得体の知れない連中がウロウロしてるんでなく
山というのはそれより身近で且つ危害を与えてくるのも身近な連中ってこと >>698
うちの70代の爺さんもノートPCで5chの専門板見てるからそれより上もいるかもしれんな 歴史ロマンを大切にしようよ
山村の人はみんな化外の民にすればロマンがあるじゃないか
山の畑で半自給自足して、たまに炭とか蕨の紐を売りに来る人は化外の人。
妙に小金を欲しがる超ド田舎民だと夢もロマンもないから、とりあえず化外の民にしよう
山村のおっさんが泊りがけで山に入って木を切って炭にする
もうこれは普通の人じゃない。サンカと言い切って良い。
>>788
炭焼きとタバコが廃れて山村は死んだんだよな >>897
江戸時代のそれは木こりの業務の一部で、煮炊き燃料の為の柴刈やろ >>915
専門板の過疎化が激しいから
年寄りはこういうスレが立つとつい懐かしくなっちゃうんだろう ただのホームレスだろ
元は落ち武者
山に住んだりしてんだろ
>>15
沖浦和光の「瀬戸内の民俗誌」に「家船」というのが出る
同じ著者の「幻の漂泊民・サンカ」も良い ド田舎だと40年前ぐらいだとガチで山賊みたいな奴らがいたもんな
まあ山んなかにいるホームレスみたいなもんだが
サンカって江戸川乱歩や坂口安吾の小説に出て来たな。
サンカは小説で読んだわ
俺が読んだ小説ではサンカは超能力持ってたトンデモ内容だったけどw
ケンモ板でこんなスレが伸びるのいいよね
忍者みたいにいるにはいたけど尾ひれがついていった感じやろ
>>700
スピードスケートの黒岩一族が忍者の末裔だとか噂というか都市伝説があったな まあ忍者でもあり異民族でもあり
人間の幻想というか、もっと言うと恐怖心が常に「敵」を作り上げるというモデルの典型的な例なんだよなこれ
>>1
ひでえなこの役所
なんで通帳預かって死ぬまで金引き出させなかったの? 日本人は昭和まで天狗だ狐だ神隠しだ言ってたレベルだから
恐怖か、それを利用する人間が「特定の民族」さえ作りあげてしまう
ロマンってのは厄介なものでマイノリティや異文化の人間は自分とはまるで異質な生活を送っていてほしいという願望が誰の内にもあるんだよね
アイヌも沖縄人もこれにやられてる
ある種のオリエンタリズムだな
定住民が、そうでない人を恐れるという心理構造
んでこれが「当然」だと思っているのが日本人なんだけど・・・
>>889
熊野や出羽三山は修験道の聖地だから修験者や山伏なんて今でも幾らでも居るぞ
法螺貝吹いてるようなのだって偶にテレビに出てるよ てかNHKのムツ婆さんでお馴染みの秩父の楢尾集落なんて当に炭焼きと細々とした農業で暮らしてきた山村じゃん
今や廃村になっちゃったけどこんなのが昔は日本中にあった訳で
そんな流浪の民が入り込む余地なんか実際ないんだよ
>>938
どういう時代を想定してるか知らんけど、結構違うよそれ 江戸時代の山奥
炭焼きだけでなく、漆器の材料を求めて職人が山を巡る
ケヤキやブナやトチノキを求め村と契約して年に何本切るか決めて金を払う
金の世の中...夢もロマンもあったもんじゃねえ
>>940
そういうのだけでもないです~
聖とか調べてみてください。江戸時代でもなくはない そんな山で修行した人に祈禱してもらって金とられるのって陰鬱だよな
同じ金使うのでも都会なら門付け芸人に面白いことしてもらえるのによ
ズッコケ三人組で山の民みたいなのいたような気もするけどそれなの?
>>944
次スレは自分で立てたらいいじゃん
それとも60以上もレスしたから満足したんか >>947
まあそのうち建つんじゃね
日本でも「海の民」の方のとか 海と川も含めて、日本というこの島国の歴史は本当はどういうものだったのか?とかやつスレが建つことは期待してるよ
藤子不二雄のフータくんに三角くんて出てたな三角寛の事かな?忘れたけど
このスレではまだ主に仏教を中心に、国家ではない存在の認識が足りないんだわ
今の俺らからすると、国と法律というものが常に一元にあるものだと思いがちだけど
山中で突然彼岸花が群生してたらそこは昔集落があったとか
村娘を輪姦して気が触れたら狐に憑かれたといってまた輪姦
村に天変地異が起これば天狗の仕業だと村の神様に祈祷
見知らぬ者がやってくれば山窩だと町中騒ぐ蝶々サンバジグザグサンバあいつの噂でチャンバも走る
高野聖も多くは偽物で放浪してる乞食だったし
江戸期になっても人別帳に載ってない人なんて五万といたはず
サンカというと途端に胡散臭くなる
>>177
だから木地師は「朱雀天皇の綸旨で山林伐採勅許があるから」みたいな偽文書を代々伝えていた。
それだけじゃなくて、時の権力者に便利がられるような特殊技能もあったんだろうけど。 >>956
マタギもそういう感じの古史古伝があるな
読み書きすら出きなさそうな人達がわりとインテリな設定もってるのって面白いよな
どこで誰がそういうのを勉強して考えたんだろうという気になる 漂泊民の集団が居たことは確かでも、独自の民族扱いまでするのはでっち上げだろ
もっともそういうでっち上げも世界中の近代国家で見られるパターンだけど
>>958
「後狩詞記」の世界やね。
柳田によると、江戸時代の国学者たちが地域の素朴な伝承を記紀神話で説明するような牽強付会を行ったらしい。
「このお社の神様は山神様ですだ」→「山の神というと大山祇命のことだな」みたいな 俺の家は元は岐阜の山間部に住んでた平家の落ち武者の集落出身だわ
俺の曾祖父さんが屯田兵として北海道に入植した
もう元の集落は跡形も無いんだろうな
>>890
柳田は「隠れ里」についても、そういうものが実際にあったとも、信仰や迷信の反映に過ぎないとも取れるようなどっちつかずな書き方してるよね。
登山やって古い山書読んでると、驚くほど山奥に旧道や集落跡があることにも驚くけど、マタギのような平地民とは区別された特殊な人々しか知らないような山域もまた有ったのではないかと感じる。 四国山脈の奥深くに有った小さな村落にまつわる伝承
明治時代に入り戸籍作成のために役人が訪れたところ、平家の落人部落であったその村の女人は正装の十二単衣で出迎えたという
平家の落人設定が謎
平家一門が悉く根絶やしにされた訳でもないし
人里離れた山中に籠る必要が無い
50年前までいた割には言語の収集が断片的なのがなー
アイヌは結構前から収集されてたし音声まで録音で残ってるのにな
>>964
壇ノ浦で終わったって認識の人にとってはそうかもしれないけどその後も散発的に平家方の反乱起きてるからね >>964
平家物語はポピュラーだったし
室町時代に南朝後裔、
江戸時代に豊臣家や他の滅亡大名、あるいは隠れキリシタンと称するのは
多少なりとも危険が伴うけど
平家残党なら公権力に追求される恐れが皆無
辺鄙な土地に住んでる人々の自尊心を満たすのに適当だったんでしょ
信長みたいに政治的意図を持って平家末裔に仮託した連中とか
隠れ里伝承と結びついていたりして、平家の落人伝承も色々複雑だな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。